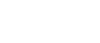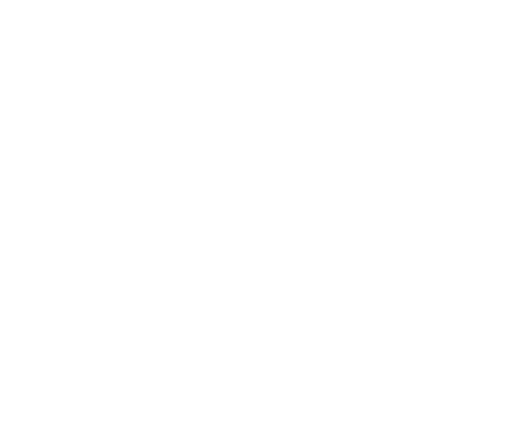2016年10月2日13:00KICK OFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原 1−2 AC長野パルセイロ
[得点]
相模原:68分岩渕良太
長 野:6分、38分佐藤悠希
|チームがアグレッシブさを失った理由
SC相模原は、前回出た課題を解こうと臨んだが、残念ながら最良の答えを導き出すことはできなかった。
10月2日、SC相模原はホームにAC長野パルセイロを迎えてJ3リーグ第24節を戦ったが、2回のPKによる失点に泣き、1−2で競り負けた。これで就任4試合目となった安永聡太郎監督の初勝利は、またしてもお預けとなり1分3敗。チームとしても6試合勝ち星から遠ざかる状況となった。
1−3で敗れた前節のFC琉球戦では試合終盤に2失点を許して1−3と敗戦した。4−3−2システムで臨んだその試合、前線から果敢にプレスを掛け、高い位置を取った両SBが度々サイドハーフを追い越す攻撃参加を見せると、前半は相手を圧倒した。ただし、かなりの運動量を求められるそのサッカーは、徐々に選手たちの体力を奪うと、後半は押し込まれ、試合終盤になると息切れするかのように失点を重ねた。
そうした課題を踏まえての長野戦だった。だから指揮官は、今節を戦うに当たって選手たちに新たなるテーマを与え、それに伴うトレーニングも行ってきた。その試みは試合後に語られた言葉にヒントがある。
「相手は前から強烈なプレスを掛けてこないというところで、1枚のボランチでうまくボールを動かしながら両ワイドも少しだけビルドアップに加わってもいいよという話で試合に入りました」
プラン通りに“こと”が運ばなかったのは、開始わずか6分でPKを与え、追いかける展開を強いられたことも要因の一つだろう。ただ、それ以上に大きかったのは、ビルドアップを試みたことにより、チームの重心が大きく下がったことにあった。
 |チームの重心が下がったことで攻撃は停滞した
|チームの重心が下がったことで攻撃は停滞した
長野戦は、右WBに深井正樹、左WBに普光院誠を起用して、中盤の底に菊岡拓朗が入ると、その近くに井上平、岩渕良太を配置する3−5−2システムで臨んだ。
前節、標榜するサッカーを90分間続けることが体力的に難しいと判断したからこそ、安永監督は、後方からビルドアップすることを選手たちに課した。そこには、常に縦へ縦へと急ぐのではなく、ボールを回せるところではボールを回し、うまくゲームを運ぼうという意図があった。今までどおり「困ったときには服部(康平)に放り込んでもOK」という指示も出ていたし、これまでチームとして築いてきた「アグレッシブにプレーする」「同サイドで攻め切る」「チャレンジする」という基盤があってのことである。
ただ、状況に応じて後方からのビルドアップを許可されたチームは、重心を大きく“後ろ”に置いてしまった。前節は左SBとして果敢な攻撃参加を見せていた普光院が飛び出す場面は激減し、むしろ左サイドを再三突破された。右サイドも低い位置からスタートするため、深井がボールを受けても、クロスを挙げるには至らない。守備時は5バックになっても攻撃時は3バックになり、全体的に高い位置を取ることで前に厚みを出すはずが、後方から攻め始めるため攻撃に迫力が出ない。服部はロングボールを待ち、石田雅俊、井上、岩渕がセカンドボールを狙おうとしたが、アンカーを担った菊岡拓朗との間に距離ができ、前半から間延びするような状況に陥った。かつ服部を競らそうとロングボールを入れても、2列目はDFの前にあるスペースから走り込むのではなく、服部と並んで拾おうとするからセカンドボールも奪えなかった。
指揮官はその事態をこう分析する。
「ビルドアップをOKにしたことで、チーム全体が一気に重くなってしまった。前節は30分で足が止まってしまったことを考えて、本当はここまでの4試合は、DFの背後というところをテーマにしたいと思っていたんだけど、自分の中で同じ過ちは繰り返したくないというチャレンジのもとで指導しているから、ビルドアップして、楽になる時間を作ろうという考えの元に下した判断だった。相手も引くし、これまでは同サイドでやり切れとしか言ってなかったんだけど、それは前提の上で、苦しくなったら、やり直してもいいと言った。そうしたら、ひとつ持ち出して相手に突かれたら、みんながみんな、やり直し始めたから、これは重たいと感じていた。まさか、ここまで一つの言葉にとらわれすぎるかと」
38分には、チームとしてのバランスの悪さが響いて2本目のPKを与えてしまった。深井正樹がその場面を振り返る。
「監督が言っているボールの捨て方というところでの判断が今日は悪かった。自分たちが高い位置を取ろうとした瞬間に、またボールを奪われるから、そのスペースを使われてしまう。PKを取られたシーンも、行けると思って上がった瞬間にパスを出されて戻った場面でしたからね」
 |積み重ねつつ次のステップへ
|積み重ねつつ次のステップへ
後半になり得点の匂いが増したのは、そのポジショニングが修正されたからだ。両WBが高い位置を取りサイドから攻撃を仕掛けられるようになった。加えて前半よりもコンパクトになり、中央でも選手たちが近い距離にいることで、相手ゴールに迫れる機会が格段に増えた。
すっかり最終ラインが板に付いてきた坂井洋平が試合を振り返る。
「前半はくさびのパスを入れようとしても距離が遠くて、それを相手に狙われて逆にカウンターを食らってしまった。後半は縦に入れても、みんなの距離が近かったからそのパスが通った。服部が最終ラインと競って深みを作るのはいいですけど、その他の選手は距離を縮めないと。みんながみんな服部の周りにいたら、全体の距離は遠くなっていく。重かったですよね、重心が。個人の戦術理解の問題もあるとは思うんですけど、約束ごとを決めるというか、細かいところまで落とし込んでいく必要がある」
後半押し込めたのは、0−2になり相手が引き、必然的に攻められる状況が用意されたということもある。システム変更やポジション変更しながらも90分間出場した井上はこう語る。
「低い位置でボールを回そうとしたけど、結局、できなくて、服部に蹴るしかなくなった前半だった。それならば、今までのようにラインを上げながら服部に入れたほうが良かったかもしれない。結果的にどっちつかずでしたよね。後半のほうが距離感は良かったかもしれないけど、最後のところでクロスが上がってこなかった。ドリブラーも多くて、FWとしてはどのタイミングでパスが出てくるのか分からず、準備が難しかった。ゴール前では自由を与えられているけど、正直、僕らのレベルでは自由があっても、その自由を活かしきれないところもあるかもしれない。そこはチームとしての約束ごとがあってもいいかもしれない」
選手からそうした意見が出る中で、安永監督も今日の敗戦を受けて、次なるテーマを考えてはいる。
「最後のところでどうするかという質は、個の能力だとは思っているけど、4試合で3得点という現状を考えたら、約束ごとを作ったほうがいいのかなとも考えている。ビルドアップの仕方もそうだし、攻撃のところも、ここで1週間空くので、考えていきたい」
課題を克服しようと臨んだ長野戦では、新たなことにチャレンジした結果、新たなる課題が露呈した。ただ、それはチームとして成長しようとする過程で試行錯誤しているからこそ見えてきた課題である。安永監督が掲げるサッカーは、選手たちに高いインテリジェンスが求められる。今、すべてを築いている段階にあるチームだけに、その成長曲線は緩やかかもしれない。ただ、指揮官は「同じ過ちは繰り返したくない」と語っているように、毎試合、少しずつではあっても、前進していることだけは確かだ。
シーズンは終わりが近づきつつあるが、SC相模原は今、生みの苦しみを味わっている。

 2016年10月2日13:00KICK OFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原 1−2 AC長野パルセイロ
[得点]
相模原:68分岩渕良太
長 野:6分、38分佐藤悠希
|チームがアグレッシブさを失った理由
SC相模原は、前回出た課題を解こうと臨んだが、残念ながら最良の答えを導き出すことはできなかった。
10月2日、SC相模原はホームにAC長野パルセイロを迎えてJ3リーグ第24節を戦ったが、2回のPKによる失点に泣き、1−2で競り負けた。これで就任4試合目となった安永聡太郎監督の初勝利は、またしてもお預けとなり1分3敗。チームとしても6試合勝ち星から遠ざかる状況となった。
1−3で敗れた前節のFC琉球戦では試合終盤に2失点を許して1−3と敗戦した。4−3−2システムで臨んだその試合、前線から果敢にプレスを掛け、高い位置を取った両SBが度々サイドハーフを追い越す攻撃参加を見せると、前半は相手を圧倒した。ただし、かなりの運動量を求められるそのサッカーは、徐々に選手たちの体力を奪うと、後半は押し込まれ、試合終盤になると息切れするかのように失点を重ねた。
そうした課題を踏まえての長野戦だった。だから指揮官は、今節を戦うに当たって選手たちに新たなるテーマを与え、それに伴うトレーニングも行ってきた。その試みは試合後に語られた言葉にヒントがある。
「相手は前から強烈なプレスを掛けてこないというところで、1枚のボランチでうまくボールを動かしながら両ワイドも少しだけビルドアップに加わってもいいよという話で試合に入りました」
プラン通りに“こと”が運ばなかったのは、開始わずか6分でPKを与え、追いかける展開を強いられたことも要因の一つだろう。ただ、それ以上に大きかったのは、ビルドアップを試みたことにより、チームの重心が大きく下がったことにあった。
2016年10月2日13:00KICK OFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原 1−2 AC長野パルセイロ
[得点]
相模原:68分岩渕良太
長 野:6分、38分佐藤悠希
|チームがアグレッシブさを失った理由
SC相模原は、前回出た課題を解こうと臨んだが、残念ながら最良の答えを導き出すことはできなかった。
10月2日、SC相模原はホームにAC長野パルセイロを迎えてJ3リーグ第24節を戦ったが、2回のPKによる失点に泣き、1−2で競り負けた。これで就任4試合目となった安永聡太郎監督の初勝利は、またしてもお預けとなり1分3敗。チームとしても6試合勝ち星から遠ざかる状況となった。
1−3で敗れた前節のFC琉球戦では試合終盤に2失点を許して1−3と敗戦した。4−3−2システムで臨んだその試合、前線から果敢にプレスを掛け、高い位置を取った両SBが度々サイドハーフを追い越す攻撃参加を見せると、前半は相手を圧倒した。ただし、かなりの運動量を求められるそのサッカーは、徐々に選手たちの体力を奪うと、後半は押し込まれ、試合終盤になると息切れするかのように失点を重ねた。
そうした課題を踏まえての長野戦だった。だから指揮官は、今節を戦うに当たって選手たちに新たなるテーマを与え、それに伴うトレーニングも行ってきた。その試みは試合後に語られた言葉にヒントがある。
「相手は前から強烈なプレスを掛けてこないというところで、1枚のボランチでうまくボールを動かしながら両ワイドも少しだけビルドアップに加わってもいいよという話で試合に入りました」
プラン通りに“こと”が運ばなかったのは、開始わずか6分でPKを与え、追いかける展開を強いられたことも要因の一つだろう。ただ、それ以上に大きかったのは、ビルドアップを試みたことにより、チームの重心が大きく下がったことにあった。
 |チームの重心が下がったことで攻撃は停滞した
長野戦は、右WBに深井正樹、左WBに普光院誠を起用して、中盤の底に菊岡拓朗が入ると、その近くに井上平、岩渕良太を配置する3−5−2システムで臨んだ。
前節、標榜するサッカーを90分間続けることが体力的に難しいと判断したからこそ、安永監督は、後方からビルドアップすることを選手たちに課した。そこには、常に縦へ縦へと急ぐのではなく、ボールを回せるところではボールを回し、うまくゲームを運ぼうという意図があった。今までどおり「困ったときには服部(康平)に放り込んでもOK」という指示も出ていたし、これまでチームとして築いてきた「アグレッシブにプレーする」「同サイドで攻め切る」「チャレンジする」という基盤があってのことである。
ただ、状況に応じて後方からのビルドアップを許可されたチームは、重心を大きく“後ろ”に置いてしまった。前節は左SBとして果敢な攻撃参加を見せていた普光院が飛び出す場面は激減し、むしろ左サイドを再三突破された。右サイドも低い位置からスタートするため、深井がボールを受けても、クロスを挙げるには至らない。守備時は5バックになっても攻撃時は3バックになり、全体的に高い位置を取ることで前に厚みを出すはずが、後方から攻め始めるため攻撃に迫力が出ない。服部はロングボールを待ち、石田雅俊、井上、岩渕がセカンドボールを狙おうとしたが、アンカーを担った菊岡拓朗との間に距離ができ、前半から間延びするような状況に陥った。かつ服部を競らそうとロングボールを入れても、2列目はDFの前にあるスペースから走り込むのではなく、服部と並んで拾おうとするからセカンドボールも奪えなかった。
指揮官はその事態をこう分析する。
「ビルドアップをOKにしたことで、チーム全体が一気に重くなってしまった。前節は30分で足が止まってしまったことを考えて、本当はここまでの4試合は、DFの背後というところをテーマにしたいと思っていたんだけど、自分の中で同じ過ちは繰り返したくないというチャレンジのもとで指導しているから、ビルドアップして、楽になる時間を作ろうという考えの元に下した判断だった。相手も引くし、これまでは同サイドでやり切れとしか言ってなかったんだけど、それは前提の上で、苦しくなったら、やり直してもいいと言った。そうしたら、ひとつ持ち出して相手に突かれたら、みんながみんな、やり直し始めたから、これは重たいと感じていた。まさか、ここまで一つの言葉にとらわれすぎるかと」
38分には、チームとしてのバランスの悪さが響いて2本目のPKを与えてしまった。深井正樹がその場面を振り返る。
「監督が言っているボールの捨て方というところでの判断が今日は悪かった。自分たちが高い位置を取ろうとした瞬間に、またボールを奪われるから、そのスペースを使われてしまう。PKを取られたシーンも、行けると思って上がった瞬間にパスを出されて戻った場面でしたからね」
|チームの重心が下がったことで攻撃は停滞した
長野戦は、右WBに深井正樹、左WBに普光院誠を起用して、中盤の底に菊岡拓朗が入ると、その近くに井上平、岩渕良太を配置する3−5−2システムで臨んだ。
前節、標榜するサッカーを90分間続けることが体力的に難しいと判断したからこそ、安永監督は、後方からビルドアップすることを選手たちに課した。そこには、常に縦へ縦へと急ぐのではなく、ボールを回せるところではボールを回し、うまくゲームを運ぼうという意図があった。今までどおり「困ったときには服部(康平)に放り込んでもOK」という指示も出ていたし、これまでチームとして築いてきた「アグレッシブにプレーする」「同サイドで攻め切る」「チャレンジする」という基盤があってのことである。
ただ、状況に応じて後方からのビルドアップを許可されたチームは、重心を大きく“後ろ”に置いてしまった。前節は左SBとして果敢な攻撃参加を見せていた普光院が飛び出す場面は激減し、むしろ左サイドを再三突破された。右サイドも低い位置からスタートするため、深井がボールを受けても、クロスを挙げるには至らない。守備時は5バックになっても攻撃時は3バックになり、全体的に高い位置を取ることで前に厚みを出すはずが、後方から攻め始めるため攻撃に迫力が出ない。服部はロングボールを待ち、石田雅俊、井上、岩渕がセカンドボールを狙おうとしたが、アンカーを担った菊岡拓朗との間に距離ができ、前半から間延びするような状況に陥った。かつ服部を競らそうとロングボールを入れても、2列目はDFの前にあるスペースから走り込むのではなく、服部と並んで拾おうとするからセカンドボールも奪えなかった。
指揮官はその事態をこう分析する。
「ビルドアップをOKにしたことで、チーム全体が一気に重くなってしまった。前節は30分で足が止まってしまったことを考えて、本当はここまでの4試合は、DFの背後というところをテーマにしたいと思っていたんだけど、自分の中で同じ過ちは繰り返したくないというチャレンジのもとで指導しているから、ビルドアップして、楽になる時間を作ろうという考えの元に下した判断だった。相手も引くし、これまでは同サイドでやり切れとしか言ってなかったんだけど、それは前提の上で、苦しくなったら、やり直してもいいと言った。そうしたら、ひとつ持ち出して相手に突かれたら、みんながみんな、やり直し始めたから、これは重たいと感じていた。まさか、ここまで一つの言葉にとらわれすぎるかと」
38分には、チームとしてのバランスの悪さが響いて2本目のPKを与えてしまった。深井正樹がその場面を振り返る。
「監督が言っているボールの捨て方というところでの判断が今日は悪かった。自分たちが高い位置を取ろうとした瞬間に、またボールを奪われるから、そのスペースを使われてしまう。PKを取られたシーンも、行けると思って上がった瞬間にパスを出されて戻った場面でしたからね」
 |積み重ねつつ次のステップへ
後半になり得点の匂いが増したのは、そのポジショニングが修正されたからだ。両WBが高い位置を取りサイドから攻撃を仕掛けられるようになった。加えて前半よりもコンパクトになり、中央でも選手たちが近い距離にいることで、相手ゴールに迫れる機会が格段に増えた。
すっかり最終ラインが板に付いてきた坂井洋平が試合を振り返る。
「前半はくさびのパスを入れようとしても距離が遠くて、それを相手に狙われて逆にカウンターを食らってしまった。後半は縦に入れても、みんなの距離が近かったからそのパスが通った。服部が最終ラインと競って深みを作るのはいいですけど、その他の選手は距離を縮めないと。みんながみんな服部の周りにいたら、全体の距離は遠くなっていく。重かったですよね、重心が。個人の戦術理解の問題もあるとは思うんですけど、約束ごとを決めるというか、細かいところまで落とし込んでいく必要がある」
後半押し込めたのは、0−2になり相手が引き、必然的に攻められる状況が用意されたということもある。システム変更やポジション変更しながらも90分間出場した井上はこう語る。
「低い位置でボールを回そうとしたけど、結局、できなくて、服部に蹴るしかなくなった前半だった。それならば、今までのようにラインを上げながら服部に入れたほうが良かったかもしれない。結果的にどっちつかずでしたよね。後半のほうが距離感は良かったかもしれないけど、最後のところでクロスが上がってこなかった。ドリブラーも多くて、FWとしてはどのタイミングでパスが出てくるのか分からず、準備が難しかった。ゴール前では自由を与えられているけど、正直、僕らのレベルでは自由があっても、その自由を活かしきれないところもあるかもしれない。そこはチームとしての約束ごとがあってもいいかもしれない」
選手からそうした意見が出る中で、安永監督も今日の敗戦を受けて、次なるテーマを考えてはいる。
「最後のところでどうするかという質は、個の能力だとは思っているけど、4試合で3得点という現状を考えたら、約束ごとを作ったほうがいいのかなとも考えている。ビルドアップの仕方もそうだし、攻撃のところも、ここで1週間空くので、考えていきたい」
課題を克服しようと臨んだ長野戦では、新たなことにチャレンジした結果、新たなる課題が露呈した。ただ、それはチームとして成長しようとする過程で試行錯誤しているからこそ見えてきた課題である。安永監督が掲げるサッカーは、選手たちに高いインテリジェンスが求められる。今、すべてを築いている段階にあるチームだけに、その成長曲線は緩やかかもしれない。ただ、指揮官は「同じ過ちは繰り返したくない」と語っているように、毎試合、少しずつではあっても、前進していることだけは確かだ。
シーズンは終わりが近づきつつあるが、SC相模原は今、生みの苦しみを味わっている。
|積み重ねつつ次のステップへ
後半になり得点の匂いが増したのは、そのポジショニングが修正されたからだ。両WBが高い位置を取りサイドから攻撃を仕掛けられるようになった。加えて前半よりもコンパクトになり、中央でも選手たちが近い距離にいることで、相手ゴールに迫れる機会が格段に増えた。
すっかり最終ラインが板に付いてきた坂井洋平が試合を振り返る。
「前半はくさびのパスを入れようとしても距離が遠くて、それを相手に狙われて逆にカウンターを食らってしまった。後半は縦に入れても、みんなの距離が近かったからそのパスが通った。服部が最終ラインと競って深みを作るのはいいですけど、その他の選手は距離を縮めないと。みんながみんな服部の周りにいたら、全体の距離は遠くなっていく。重かったですよね、重心が。個人の戦術理解の問題もあるとは思うんですけど、約束ごとを決めるというか、細かいところまで落とし込んでいく必要がある」
後半押し込めたのは、0−2になり相手が引き、必然的に攻められる状況が用意されたということもある。システム変更やポジション変更しながらも90分間出場した井上はこう語る。
「低い位置でボールを回そうとしたけど、結局、できなくて、服部に蹴るしかなくなった前半だった。それならば、今までのようにラインを上げながら服部に入れたほうが良かったかもしれない。結果的にどっちつかずでしたよね。後半のほうが距離感は良かったかもしれないけど、最後のところでクロスが上がってこなかった。ドリブラーも多くて、FWとしてはどのタイミングでパスが出てくるのか分からず、準備が難しかった。ゴール前では自由を与えられているけど、正直、僕らのレベルでは自由があっても、その自由を活かしきれないところもあるかもしれない。そこはチームとしての約束ごとがあってもいいかもしれない」
選手からそうした意見が出る中で、安永監督も今日の敗戦を受けて、次なるテーマを考えてはいる。
「最後のところでどうするかという質は、個の能力だとは思っているけど、4試合で3得点という現状を考えたら、約束ごとを作ったほうがいいのかなとも考えている。ビルドアップの仕方もそうだし、攻撃のところも、ここで1週間空くので、考えていきたい」
課題を克服しようと臨んだ長野戦では、新たなことにチャレンジした結果、新たなる課題が露呈した。ただ、それはチームとして成長しようとする過程で試行錯誤しているからこそ見えてきた課題である。安永監督が掲げるサッカーは、選手たちに高いインテリジェンスが求められる。今、すべてを築いている段階にあるチームだけに、その成長曲線は緩やかかもしれない。ただ、指揮官は「同じ過ちは繰り返したくない」と語っているように、毎試合、少しずつではあっても、前進していることだけは確かだ。
シーズンは終わりが近づきつつあるが、SC相模原は今、生みの苦しみを味わっている。