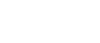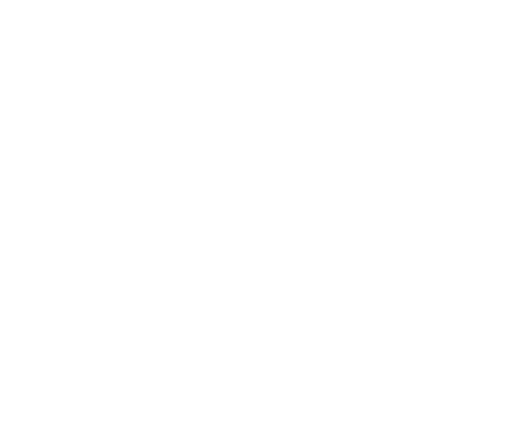2015明治安田生命J3リーグ第27節
2015年9月6日 13:00KICK OFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原2−2グルージャ盛岡
[得点]
相模原:73分服部康平、88分成田恭輔
盛 岡:6分林勇介、32分松田賢太
 |後半追い上げ引き分けも喜べない試合
|後半追い上げ引き分けも喜べない試合
取材ノートには、こう走り書きしてある。
<自滅。距離感が悪い。連動性がない>
続いて、こうも記していた。
<崩されているのではなく、相手は崩して得点しようともしていない>
SC相模原は、2−0の状況で試合を折り返すと、途中出場したFW服部康平とMF成田恭輔の得点で追いつき、グルージャ盛岡に引き分けた。特に成田が88分に放った豪快なミドルシュートがあまりに鮮やかだったため、勝利した錯覚にすら陥ったが、SC相模原はホームで勝ち点1しか拾えなかった。これによりリーグ戦は7試合未勝利——最後に勝利したのは7月5日、J3リーグ第19節のYS横浜戦で、あれから2カ月も歓喜から遠ざかっている。
FW高原直泰に加えてDF森勇介、さらにはDF天野恒太、DF工藤祐生、DF安藝正俊と、主力の多くをケガで欠いている。加えてDF小谷祐喜も今節は出場停止だった。そのためボランチが本職の須藤右介をCBに抜擢し、ボランチには曽我部慶太を起用しなければならない事態に、チームは陥っている。そうした苦しい状況を十分に理解しながらも、やはりももどかしさが残る試合でしかなかった。いくら途中出場した選手が得点を決めて同点に追いついたとはいえ、前半の不出来は帳消しにはならない。
 |警戒していた立ち上がり早々に失点
|警戒していた立ち上がり早々に失点
指揮官の辛島啓珠監督は、盛岡の特長を鑑みて、試合前の選手たちに「先に失点してしまうと、試合的に厳しくなるから絶対に注意するように」との指示を送っていたという。だが、SC相模原は開始6分という早い時間帯に失点する。盛岡のFW工藤光輝に斜めにパスを通されると、走り込んだ林勇介に間を突破され、左足であっさりと得点を許してしまう。
マークが緩く、守備のポジショニングが甘く、さらには判断も遅いことによる失点だった。相手がDFの背後を狙ってくる、もしくは斜めに進入してくることは想定していたはずだ。にもかかわらず、対応の悪さにより自滅ともいえる形から失点した。
リードを奪った盛岡は、組織的な守備をベースにした戦い方へあっさりと移行できた。SC相模原は、本職ではない須藤がCBを、曽我部がボランチを務めている状況もあり、「後方でボールを回して、ボランチから縦パスを入れようという狙いがあった」(辛島監督)というが、一度、ブロックを作って攻撃を防いでから打って出る盛岡の戦術に為す術がなくなった。
 |自滅ともいえる形から2失点目を喫する
|自滅ともいえる形から2失点目を喫する
32分にはこれまた自滅ともいえる形から失点した。自分たちのスローインをマイボールにできず、相手に展開されると、先制点を許した林から松田賢太につながれ、失点した。これもマークが甘く、斜めに走られると、今度は進入される前にDFとDFの間からシュートを許した格好となった。
42分にFW樋口寛規が決定機を外すなど、SC相模原もチャンスがなかったわけではない。だが、辛島監督も「3点目が決まっていたら、試合は終わっていたかもしれない」と話したように、GK佐藤健のファインセーブもあり、よく2失点に抑えたという表現のほうが正しいだろう。
確かに盛岡に崩された場面は少ない。だが、盛岡は多彩なパスワークで守備を崩すのではなく、シンプルに斜めに走り込む、DFの裏を狙うことで、SC相模原のゴールに的確に迫っていた。
SC相模原は後半もメンバー交代せずにスタートしたが、結果的に前半と状況は変わらなかった。反撃に出たのは58分に飯田涼と樋口を下げ、服部とMF北原毅之を送り込んでからだ。前線がタレスと服部という明確なターゲットになったことで、サイドからのクロスやロングボールに競り勝つ回数が増えたことと、相手の運動量が落ちたことで攻勢になった、いわばパワープレーにすぎなかった。ようするに自分たちが意図していたサッカーでは、攻撃の糸口すら作れなかった試合だったということだ。
繰り返すが確かに成田のミドルシュートは思わず息をのむほど、「スーパー」なものであった。同点に追いついた結果も、0−2で敗戦するよりは遥かにポジティブな結果だ。しかし、立ち上がりに失点してから、チームとしてやるべきことがピッチで表現できなかったことは深刻である。
再三の好セーブでチームを救った佐藤も「結局、いまの現状が出てしまった。サッカーに対して取り組む姿勢の甘さが失点に表れている。追いついたからOKという空気になってしまってはいけない。勝てるゲームをしていかないと」と、現状に警鐘を鳴らした。2失点に猛省したDFフェアー・モービーも「選手同士の距離感が悪かった。試合中のコミュニケーションが少ないし、みんながみんな、個でやっているだけになっている」と指摘した。不慣れなCBで奮闘した須藤も「チーム戦術うんぬんの前に僕も含めて一人ひとりのプレーを考えていかなければならない。失点は個人戦術のところでもあった。選手個々が反省と課題を明確しなければならい」と、試合の出来を悔やんだ。
選手一人ひとりに話を聞けば、課題を口にし、やるべきこともやらなければならないことも理解している。ただ、これがピッチ上になると意思疎通が乏しくなり、チームとして機能しなくなる。
 |単純なことの積み重ねがいまのチームに必要
|単純なことの積み重ねがいまのチームに必要
順位だけを見れば盛岡は11位であり、4位で踏みとどまっているSC相模原よりも下に位置している。だが、チームとしての徹底はSC相模原よりも明確だった。
観客が1882人だったということもあり、いつも以上にピッチでのやりとりがメインスタンドまで届いてきたが、声を掛け合っているのは、盛岡のそればかりだった。SC相模原は、個々に話はしているが、失点したときも、うまくいっていないときも、チーム全体に声を掛けるような建設的なコミュニケーションは希薄だった。
たまたま今週、J1のあるクラブに赴き、ある選手の取材をする機会に恵まれた。その選手は「単純なことかもしれないですけど、チームメイトを褒めたり、守備のコーチングをしたりするだけで、チーム全体が手に取るように変わっていくのが分かるんです」と語っていた。
声やコーチングなどは、根本を大きく変える要素ではないかもしれない。だが、そうした単純でシンプルなことの積み重ねが、チームを変えていくことにつながっている。リーグ戦7試合未勝利であり、2カ月以上も歓喜から遠ざかっているサポーターは、後半追い上げ、引き分けたことに拍手を送ってくれた。
この試合の取材ノートの最後に筆者はこう殴り書きした。
<SC相模原のサポーターはブーイングをしない。その優しさにチームは、選手たちは、結果で答えるべきだ。心のブーイングをそれぞれが感じなければ、何も変わらないのではないか>
 |後半追い上げ引き分けも喜べない試合
取材ノートには、こう走り書きしてある。
<自滅。距離感が悪い。連動性がない>
続いて、こうも記していた。
<崩されているのではなく、相手は崩して得点しようともしていない>
SC相模原は、2−0の状況で試合を折り返すと、途中出場したFW服部康平とMF成田恭輔の得点で追いつき、グルージャ盛岡に引き分けた。特に成田が88分に放った豪快なミドルシュートがあまりに鮮やかだったため、勝利した錯覚にすら陥ったが、SC相模原はホームで勝ち点1しか拾えなかった。これによりリーグ戦は7試合未勝利——最後に勝利したのは7月5日、J3リーグ第19節のYS横浜戦で、あれから2カ月も歓喜から遠ざかっている。
FW高原直泰に加えてDF森勇介、さらにはDF天野恒太、DF工藤祐生、DF安藝正俊と、主力の多くをケガで欠いている。加えてDF小谷祐喜も今節は出場停止だった。そのためボランチが本職の須藤右介をCBに抜擢し、ボランチには曽我部慶太を起用しなければならない事態に、チームは陥っている。そうした苦しい状況を十分に理解しながらも、やはりももどかしさが残る試合でしかなかった。いくら途中出場した選手が得点を決めて同点に追いついたとはいえ、前半の不出来は帳消しにはならない。
|後半追い上げ引き分けも喜べない試合
取材ノートには、こう走り書きしてある。
<自滅。距離感が悪い。連動性がない>
続いて、こうも記していた。
<崩されているのではなく、相手は崩して得点しようともしていない>
SC相模原は、2−0の状況で試合を折り返すと、途中出場したFW服部康平とMF成田恭輔の得点で追いつき、グルージャ盛岡に引き分けた。特に成田が88分に放った豪快なミドルシュートがあまりに鮮やかだったため、勝利した錯覚にすら陥ったが、SC相模原はホームで勝ち点1しか拾えなかった。これによりリーグ戦は7試合未勝利——最後に勝利したのは7月5日、J3リーグ第19節のYS横浜戦で、あれから2カ月も歓喜から遠ざかっている。
FW高原直泰に加えてDF森勇介、さらにはDF天野恒太、DF工藤祐生、DF安藝正俊と、主力の多くをケガで欠いている。加えてDF小谷祐喜も今節は出場停止だった。そのためボランチが本職の須藤右介をCBに抜擢し、ボランチには曽我部慶太を起用しなければならない事態に、チームは陥っている。そうした苦しい状況を十分に理解しながらも、やはりももどかしさが残る試合でしかなかった。いくら途中出場した選手が得点を決めて同点に追いついたとはいえ、前半の不出来は帳消しにはならない。
 |警戒していた立ち上がり早々に失点
指揮官の辛島啓珠監督は、盛岡の特長を鑑みて、試合前の選手たちに「先に失点してしまうと、試合的に厳しくなるから絶対に注意するように」との指示を送っていたという。だが、SC相模原は開始6分という早い時間帯に失点する。盛岡のFW工藤光輝に斜めにパスを通されると、走り込んだ林勇介に間を突破され、左足であっさりと得点を許してしまう。
マークが緩く、守備のポジショニングが甘く、さらには判断も遅いことによる失点だった。相手がDFの背後を狙ってくる、もしくは斜めに進入してくることは想定していたはずだ。にもかかわらず、対応の悪さにより自滅ともいえる形から失点した。
リードを奪った盛岡は、組織的な守備をベースにした戦い方へあっさりと移行できた。SC相模原は、本職ではない須藤がCBを、曽我部がボランチを務めている状況もあり、「後方でボールを回して、ボランチから縦パスを入れようという狙いがあった」(辛島監督)というが、一度、ブロックを作って攻撃を防いでから打って出る盛岡の戦術に為す術がなくなった。
|警戒していた立ち上がり早々に失点
指揮官の辛島啓珠監督は、盛岡の特長を鑑みて、試合前の選手たちに「先に失点してしまうと、試合的に厳しくなるから絶対に注意するように」との指示を送っていたという。だが、SC相模原は開始6分という早い時間帯に失点する。盛岡のFW工藤光輝に斜めにパスを通されると、走り込んだ林勇介に間を突破され、左足であっさりと得点を許してしまう。
マークが緩く、守備のポジショニングが甘く、さらには判断も遅いことによる失点だった。相手がDFの背後を狙ってくる、もしくは斜めに進入してくることは想定していたはずだ。にもかかわらず、対応の悪さにより自滅ともいえる形から失点した。
リードを奪った盛岡は、組織的な守備をベースにした戦い方へあっさりと移行できた。SC相模原は、本職ではない須藤がCBを、曽我部がボランチを務めている状況もあり、「後方でボールを回して、ボランチから縦パスを入れようという狙いがあった」(辛島監督)というが、一度、ブロックを作って攻撃を防いでから打って出る盛岡の戦術に為す術がなくなった。
 |自滅ともいえる形から2失点目を喫する
32分にはこれまた自滅ともいえる形から失点した。自分たちのスローインをマイボールにできず、相手に展開されると、先制点を許した林から松田賢太につながれ、失点した。これもマークが甘く、斜めに走られると、今度は進入される前にDFとDFの間からシュートを許した格好となった。
42分にFW樋口寛規が決定機を外すなど、SC相模原もチャンスがなかったわけではない。だが、辛島監督も「3点目が決まっていたら、試合は終わっていたかもしれない」と話したように、GK佐藤健のファインセーブもあり、よく2失点に抑えたという表現のほうが正しいだろう。
確かに盛岡に崩された場面は少ない。だが、盛岡は多彩なパスワークで守備を崩すのではなく、シンプルに斜めに走り込む、DFの裏を狙うことで、SC相模原のゴールに的確に迫っていた。
SC相模原は後半もメンバー交代せずにスタートしたが、結果的に前半と状況は変わらなかった。反撃に出たのは58分に飯田涼と樋口を下げ、服部とMF北原毅之を送り込んでからだ。前線がタレスと服部という明確なターゲットになったことで、サイドからのクロスやロングボールに競り勝つ回数が増えたことと、相手の運動量が落ちたことで攻勢になった、いわばパワープレーにすぎなかった。ようするに自分たちが意図していたサッカーでは、攻撃の糸口すら作れなかった試合だったということだ。
繰り返すが確かに成田のミドルシュートは思わず息をのむほど、「スーパー」なものであった。同点に追いついた結果も、0−2で敗戦するよりは遥かにポジティブな結果だ。しかし、立ち上がりに失点してから、チームとしてやるべきことがピッチで表現できなかったことは深刻である。
再三の好セーブでチームを救った佐藤も「結局、いまの現状が出てしまった。サッカーに対して取り組む姿勢の甘さが失点に表れている。追いついたからOKという空気になってしまってはいけない。勝てるゲームをしていかないと」と、現状に警鐘を鳴らした。2失点に猛省したDFフェアー・モービーも「選手同士の距離感が悪かった。試合中のコミュニケーションが少ないし、みんながみんな、個でやっているだけになっている」と指摘した。不慣れなCBで奮闘した須藤も「チーム戦術うんぬんの前に僕も含めて一人ひとりのプレーを考えていかなければならない。失点は個人戦術のところでもあった。選手個々が反省と課題を明確しなければならい」と、試合の出来を悔やんだ。
選手一人ひとりに話を聞けば、課題を口にし、やるべきこともやらなければならないことも理解している。ただ、これがピッチ上になると意思疎通が乏しくなり、チームとして機能しなくなる。
|自滅ともいえる形から2失点目を喫する
32分にはこれまた自滅ともいえる形から失点した。自分たちのスローインをマイボールにできず、相手に展開されると、先制点を許した林から松田賢太につながれ、失点した。これもマークが甘く、斜めに走られると、今度は進入される前にDFとDFの間からシュートを許した格好となった。
42分にFW樋口寛規が決定機を外すなど、SC相模原もチャンスがなかったわけではない。だが、辛島監督も「3点目が決まっていたら、試合は終わっていたかもしれない」と話したように、GK佐藤健のファインセーブもあり、よく2失点に抑えたという表現のほうが正しいだろう。
確かに盛岡に崩された場面は少ない。だが、盛岡は多彩なパスワークで守備を崩すのではなく、シンプルに斜めに走り込む、DFの裏を狙うことで、SC相模原のゴールに的確に迫っていた。
SC相模原は後半もメンバー交代せずにスタートしたが、結果的に前半と状況は変わらなかった。反撃に出たのは58分に飯田涼と樋口を下げ、服部とMF北原毅之を送り込んでからだ。前線がタレスと服部という明確なターゲットになったことで、サイドからのクロスやロングボールに競り勝つ回数が増えたことと、相手の運動量が落ちたことで攻勢になった、いわばパワープレーにすぎなかった。ようするに自分たちが意図していたサッカーでは、攻撃の糸口すら作れなかった試合だったということだ。
繰り返すが確かに成田のミドルシュートは思わず息をのむほど、「スーパー」なものであった。同点に追いついた結果も、0−2で敗戦するよりは遥かにポジティブな結果だ。しかし、立ち上がりに失点してから、チームとしてやるべきことがピッチで表現できなかったことは深刻である。
再三の好セーブでチームを救った佐藤も「結局、いまの現状が出てしまった。サッカーに対して取り組む姿勢の甘さが失点に表れている。追いついたからOKという空気になってしまってはいけない。勝てるゲームをしていかないと」と、現状に警鐘を鳴らした。2失点に猛省したDFフェアー・モービーも「選手同士の距離感が悪かった。試合中のコミュニケーションが少ないし、みんながみんな、個でやっているだけになっている」と指摘した。不慣れなCBで奮闘した須藤も「チーム戦術うんぬんの前に僕も含めて一人ひとりのプレーを考えていかなければならない。失点は個人戦術のところでもあった。選手個々が反省と課題を明確しなければならい」と、試合の出来を悔やんだ。
選手一人ひとりに話を聞けば、課題を口にし、やるべきこともやらなければならないことも理解している。ただ、これがピッチ上になると意思疎通が乏しくなり、チームとして機能しなくなる。
 |単純なことの積み重ねがいまのチームに必要
順位だけを見れば盛岡は11位であり、4位で踏みとどまっているSC相模原よりも下に位置している。だが、チームとしての徹底はSC相模原よりも明確だった。
観客が1882人だったということもあり、いつも以上にピッチでのやりとりがメインスタンドまで届いてきたが、声を掛け合っているのは、盛岡のそればかりだった。SC相模原は、個々に話はしているが、失点したときも、うまくいっていないときも、チーム全体に声を掛けるような建設的なコミュニケーションは希薄だった。
たまたま今週、J1のあるクラブに赴き、ある選手の取材をする機会に恵まれた。その選手は「単純なことかもしれないですけど、チームメイトを褒めたり、守備のコーチングをしたりするだけで、チーム全体が手に取るように変わっていくのが分かるんです」と語っていた。
声やコーチングなどは、根本を大きく変える要素ではないかもしれない。だが、そうした単純でシンプルなことの積み重ねが、チームを変えていくことにつながっている。リーグ戦7試合未勝利であり、2カ月以上も歓喜から遠ざかっているサポーターは、後半追い上げ、引き分けたことに拍手を送ってくれた。
この試合の取材ノートの最後に筆者はこう殴り書きした。
<SC相模原のサポーターはブーイングをしない。その優しさにチームは、選手たちは、結果で答えるべきだ。心のブーイングをそれぞれが感じなければ、何も変わらないのではないか>
|単純なことの積み重ねがいまのチームに必要
順位だけを見れば盛岡は11位であり、4位で踏みとどまっているSC相模原よりも下に位置している。だが、チームとしての徹底はSC相模原よりも明確だった。
観客が1882人だったということもあり、いつも以上にピッチでのやりとりがメインスタンドまで届いてきたが、声を掛け合っているのは、盛岡のそればかりだった。SC相模原は、個々に話はしているが、失点したときも、うまくいっていないときも、チーム全体に声を掛けるような建設的なコミュニケーションは希薄だった。
たまたま今週、J1のあるクラブに赴き、ある選手の取材をする機会に恵まれた。その選手は「単純なことかもしれないですけど、チームメイトを褒めたり、守備のコーチングをしたりするだけで、チーム全体が手に取るように変わっていくのが分かるんです」と語っていた。
声やコーチングなどは、根本を大きく変える要素ではないかもしれない。だが、そうした単純でシンプルなことの積み重ねが、チームを変えていくことにつながっている。リーグ戦7試合未勝利であり、2カ月以上も歓喜から遠ざかっているサポーターは、後半追い上げ、引き分けたことに拍手を送ってくれた。
この試合の取材ノートの最後に筆者はこう殴り書きした。
<SC相模原のサポーターはブーイングをしない。その優しさにチームは、選手たちは、結果で答えるべきだ。心のブーイングをそれぞれが感じなければ、何も変わらないのではないか>