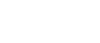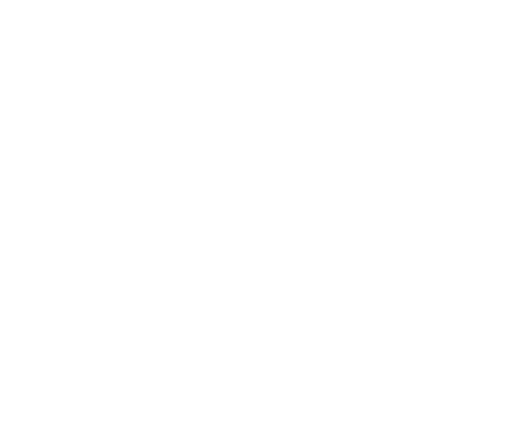2015明治安田生命J3リーグ 第4節
2015年4月5日 13:00KICK OFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原 1−1 グルージャ盛岡
[得点]
相模原:26分曽我部慶太
盛岡 :64分高橋悠馬
 |縦への意識と動きが先制点を生んだ
|縦への意識と動きが先制点を生んだ
負けに等しい引き分けだったと考えるべきか。負けずに引き分けたことをよしとするべきか。判断の難しいゲームとなった。
SC相模原は、曇天の相模原ギオンスタジアムにグルージャ盛岡を迎えた。前節の敗戦を受けて、先発には今シーズン初スタメンとなるFW服部康平が名を連ね、FW高原直泰と2トップを組んだ。4−4−2の両サイドはFW井上平とMF曽我部慶太が務め、ボランチ以下は前節から変更なし。SC相模原は、今シーズン未勝利の盛岡に対して、前半から積極的に仕掛けていった。エースの高原を中心に攻撃は機能していく。4分には高原の柔らかいクロスに服部がヘディングシュートを狙うが、惜しくもオフサイド。1分後にも服部が高原とのワンツーで突破を試みようとしたが、これもわずかにパスが合わず、決定機とはならなかった。
ただ、盛岡の鳴尾直軌監督も「前半は相手のほうが主導権を握っていた」と認めるほど、SC相模原ペースで試合は進んでいた。16分にはDF森勇介のクロスを服部が再びヘディングで狙い、21分にも井上が起点となり、森がドリブルで中に侵入すると、服部にスルーパスを狙うなど、多彩な攻撃で相手ゴールに迫った。
3−1−4−2システムを採用した盛岡も組織的な戦いを挑んできた。前線から連動したプレスを行うだけでなく、素早く帰陣するとブロックを形成して、SC相模原の攻撃を跳ね返す。ボールを奪えば、右サイドに張っているMF髙瀨証にロングボールを展開し、彼のスピードある突破からチャンスを作り出していた。マッチアップしていたDF大森啓生が抜かれる、もしくはDF工藤祐生がつり出されて折り返されると、いくつか危ない場面もあった。
それでもなお、ゲームを掌握していたのはSC相模原だった。最終ラインからも縦に早い攻撃は意識できていた。CBを務める工藤から相手DFと相手ボランチのギャップでボールを受けようとする曽我部に縦パスが入る。工藤は「どこかで攻撃のスイッチを入れなければならない。それを最終ラインからも意識して縦パスを狙っていた」と語る。受け手である曽我部も「前半は相手陣内でプレーできていたし、チャンスもあった。左サイドにいるときは、(大森)啓生が高い位置を取っているので、縦パスを受けてうまくターンできれば一発でチャンスになる。今日の試合ではDF、ボランチ含めて、うまく縦パスを当ててくれていたので、チャンスは作れていたと思う」と、前半を振り返った。前節、課題とされていた引いた相手を崩すための工夫と精度、そして質に、改善の兆しが見られた。だからこそ、26分の先制点は生まれた。
スイッチを入れたのは工藤だった。縦パスを入れると、左サイドで受けた曽我部がターンして、さらに縦のスペースに走る服部に通す。服部はシンプルに大森に預けると、走り込む曽我部にスルーパス。これは盛岡DF陣がクリアするが、再び拾うと、大森がクロス。DFに当たったこぼれ球を曽我部が右足で押し込んだ。
 |後半、3バックへ変更するが機能せずに失点
|後半、3バックへ変更するが機能せずに失点
ところが、である。後半に入ると、つかんでいた主導権を相手に渡してしまう。高原が負傷したためハーフタイムで交代を余儀なくされたこともその一因だった。また、それに伴いDFフェア・モービーを投入して、前節同様、3バックにシステム変更したことも裏目に出た。3バックになったことで、マークが曖昧になる。両サイドの大森と森がより高い位置を取ることで攻撃に厚みが出たが、その一方で、2列目とウイングバック、ウイングバックとCBなど、至るところで距離が遠くなり、そのスペースを相手に使われるようになった。それが失点につながる。
64分だった。右サイドでFW益子義浩がフリーでボールを受けると、上がってきた髙瀨に縦パスが通る。そこから髙瀨にクロスを上げられると、走り込んできたMF高橋悠馬に頭で決められて同点に追いつかれてしまう。髙瀨にパスが通った時点でマークは揺さぶられ、クロスに走り込んできた高橋に対してもゴール前には人がいたにもかかわらず、フリーでフィニッシュさせてしまった。まさに3バックに変更したことによる責任転嫁が生んだ失点だった。辛島啓珠監督も認める。
「タカ(髙原直泰)がちょっと足に問題を抱えていて交代して。そこでモービーを入れて5バックにしたんですけど、4から5にシステム変更したことによって、いい流れにならず、逆に点を取られてからも、危ないシーンがありました。それで途中からまた4バックに戻した。最終的に1−1だったんですけど、この結果の責任は自分にあります」
同点に追いつかれた後も、逆に相手にギャップを突かれて、SC相模原はピンチを招いた。指揮官も前述したように、3バックが機能しないと悟ったため、再び4バックに戻したが、ゲームの流れを今一度、引き寄せることはできなかった。
前半、流れをつかんでいただけに、追いつかれての引き分けは、敗戦のようなショックがある。指揮官も「選手たちに迷惑を掛けてしまったというのが率直なところです」と、自らの采配を悔やんだ。
 |この引き分けをチームの分岐点とすることができるか
|この引き分けをチームの分岐点とすることができるか
試合後、悔しそうな表情を浮かべスタジアムを後にする辛島監督の姿には、新たなる決意なようなものを見ることができた。何より、指揮官が自らの非を認める潔さには、清々しさすら感じる。就任から4試合で、つかんだ手応えや課題が浮き彫りになったのだろう。
そして何より、選手たちにも逞しさがある。曽我部にシステム変更による弊害があったかと尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「システム変更も少しは理由としてあるかもしれないですが、それ以上に、みんなも長くサッカーをやってきている中で、こうした状況は経験あるはず。みんな、やったことのないポジションではなかったと思うので。だからシステム変更というよりも、僕の中では完全に一人ひとりのエリアへの責任が、後半に関しては全くなくなり、引いて、怖がってしまった結果だと思います。システムというよりも個々が悪かった」
後半になり、高原が負傷したためピッチを去ると、攻撃でも高い位置でキープする選手がいなくなり、後方の上がりを促すことができなくなった。守備でも、チームとしての守備のスイッチを入れる役割がいなくなり、ボールの取りどころが分散し、連動性も曖昧になった。ここまで無得点の高原だが、いなくなって改めて存在感の大きさに気付かされる。ケガの状態は不明だが、彼がいないとき、チームとしてどのように戦っていくのか。誰が攻撃ではリーダーとなり、誰が守備ではチームを統率していくのか。チーム全体の底上げと、個々の責任感が問われていく。
1−1の引き分けではあったが、指揮官にとっても、選手たちにとっても、振り返ったとき、この試合がチームのターニングポイントだったと思える試合にすることができるか。それは次節の藤枝MYFC戦、そして4月19日にホームで行われるFC町田ゼルビアとの相武決戦で知ることができる。

 |縦への意識と動きが先制点を生んだ
負けに等しい引き分けだったと考えるべきか。負けずに引き分けたことをよしとするべきか。判断の難しいゲームとなった。
SC相模原は、曇天の相模原ギオンスタジアムにグルージャ盛岡を迎えた。前節の敗戦を受けて、先発には今シーズン初スタメンとなるFW服部康平が名を連ね、FW高原直泰と2トップを組んだ。4−4−2の両サイドはFW井上平とMF曽我部慶太が務め、ボランチ以下は前節から変更なし。SC相模原は、今シーズン未勝利の盛岡に対して、前半から積極的に仕掛けていった。エースの高原を中心に攻撃は機能していく。4分には高原の柔らかいクロスに服部がヘディングシュートを狙うが、惜しくもオフサイド。1分後にも服部が高原とのワンツーで突破を試みようとしたが、これもわずかにパスが合わず、決定機とはならなかった。
ただ、盛岡の鳴尾直軌監督も「前半は相手のほうが主導権を握っていた」と認めるほど、SC相模原ペースで試合は進んでいた。16分にはDF森勇介のクロスを服部が再びヘディングで狙い、21分にも井上が起点となり、森がドリブルで中に侵入すると、服部にスルーパスを狙うなど、多彩な攻撃で相手ゴールに迫った。
3−1−4−2システムを採用した盛岡も組織的な戦いを挑んできた。前線から連動したプレスを行うだけでなく、素早く帰陣するとブロックを形成して、SC相模原の攻撃を跳ね返す。ボールを奪えば、右サイドに張っているMF髙瀨証にロングボールを展開し、彼のスピードある突破からチャンスを作り出していた。マッチアップしていたDF大森啓生が抜かれる、もしくはDF工藤祐生がつり出されて折り返されると、いくつか危ない場面もあった。
それでもなお、ゲームを掌握していたのはSC相模原だった。最終ラインからも縦に早い攻撃は意識できていた。CBを務める工藤から相手DFと相手ボランチのギャップでボールを受けようとする曽我部に縦パスが入る。工藤は「どこかで攻撃のスイッチを入れなければならない。それを最終ラインからも意識して縦パスを狙っていた」と語る。受け手である曽我部も「前半は相手陣内でプレーできていたし、チャンスもあった。左サイドにいるときは、(大森)啓生が高い位置を取っているので、縦パスを受けてうまくターンできれば一発でチャンスになる。今日の試合ではDF、ボランチ含めて、うまく縦パスを当ててくれていたので、チャンスは作れていたと思う」と、前半を振り返った。前節、課題とされていた引いた相手を崩すための工夫と精度、そして質に、改善の兆しが見られた。だからこそ、26分の先制点は生まれた。
スイッチを入れたのは工藤だった。縦パスを入れると、左サイドで受けた曽我部がターンして、さらに縦のスペースに走る服部に通す。服部はシンプルに大森に預けると、走り込む曽我部にスルーパス。これは盛岡DF陣がクリアするが、再び拾うと、大森がクロス。DFに当たったこぼれ球を曽我部が右足で押し込んだ。
|縦への意識と動きが先制点を生んだ
負けに等しい引き分けだったと考えるべきか。負けずに引き分けたことをよしとするべきか。判断の難しいゲームとなった。
SC相模原は、曇天の相模原ギオンスタジアムにグルージャ盛岡を迎えた。前節の敗戦を受けて、先発には今シーズン初スタメンとなるFW服部康平が名を連ね、FW高原直泰と2トップを組んだ。4−4−2の両サイドはFW井上平とMF曽我部慶太が務め、ボランチ以下は前節から変更なし。SC相模原は、今シーズン未勝利の盛岡に対して、前半から積極的に仕掛けていった。エースの高原を中心に攻撃は機能していく。4分には高原の柔らかいクロスに服部がヘディングシュートを狙うが、惜しくもオフサイド。1分後にも服部が高原とのワンツーで突破を試みようとしたが、これもわずかにパスが合わず、決定機とはならなかった。
ただ、盛岡の鳴尾直軌監督も「前半は相手のほうが主導権を握っていた」と認めるほど、SC相模原ペースで試合は進んでいた。16分にはDF森勇介のクロスを服部が再びヘディングで狙い、21分にも井上が起点となり、森がドリブルで中に侵入すると、服部にスルーパスを狙うなど、多彩な攻撃で相手ゴールに迫った。
3−1−4−2システムを採用した盛岡も組織的な戦いを挑んできた。前線から連動したプレスを行うだけでなく、素早く帰陣するとブロックを形成して、SC相模原の攻撃を跳ね返す。ボールを奪えば、右サイドに張っているMF髙瀨証にロングボールを展開し、彼のスピードある突破からチャンスを作り出していた。マッチアップしていたDF大森啓生が抜かれる、もしくはDF工藤祐生がつり出されて折り返されると、いくつか危ない場面もあった。
それでもなお、ゲームを掌握していたのはSC相模原だった。最終ラインからも縦に早い攻撃は意識できていた。CBを務める工藤から相手DFと相手ボランチのギャップでボールを受けようとする曽我部に縦パスが入る。工藤は「どこかで攻撃のスイッチを入れなければならない。それを最終ラインからも意識して縦パスを狙っていた」と語る。受け手である曽我部も「前半は相手陣内でプレーできていたし、チャンスもあった。左サイドにいるときは、(大森)啓生が高い位置を取っているので、縦パスを受けてうまくターンできれば一発でチャンスになる。今日の試合ではDF、ボランチ含めて、うまく縦パスを当ててくれていたので、チャンスは作れていたと思う」と、前半を振り返った。前節、課題とされていた引いた相手を崩すための工夫と精度、そして質に、改善の兆しが見られた。だからこそ、26分の先制点は生まれた。
スイッチを入れたのは工藤だった。縦パスを入れると、左サイドで受けた曽我部がターンして、さらに縦のスペースに走る服部に通す。服部はシンプルに大森に預けると、走り込む曽我部にスルーパス。これは盛岡DF陣がクリアするが、再び拾うと、大森がクロス。DFに当たったこぼれ球を曽我部が右足で押し込んだ。
 |後半、3バックへ変更するが機能せずに失点
ところが、である。後半に入ると、つかんでいた主導権を相手に渡してしまう。高原が負傷したためハーフタイムで交代を余儀なくされたこともその一因だった。また、それに伴いDFフェア・モービーを投入して、前節同様、3バックにシステム変更したことも裏目に出た。3バックになったことで、マークが曖昧になる。両サイドの大森と森がより高い位置を取ることで攻撃に厚みが出たが、その一方で、2列目とウイングバック、ウイングバックとCBなど、至るところで距離が遠くなり、そのスペースを相手に使われるようになった。それが失点につながる。
64分だった。右サイドでFW益子義浩がフリーでボールを受けると、上がってきた髙瀨に縦パスが通る。そこから髙瀨にクロスを上げられると、走り込んできたMF高橋悠馬に頭で決められて同点に追いつかれてしまう。髙瀨にパスが通った時点でマークは揺さぶられ、クロスに走り込んできた高橋に対してもゴール前には人がいたにもかかわらず、フリーでフィニッシュさせてしまった。まさに3バックに変更したことによる責任転嫁が生んだ失点だった。辛島啓珠監督も認める。
「タカ(髙原直泰)がちょっと足に問題を抱えていて交代して。そこでモービーを入れて5バックにしたんですけど、4から5にシステム変更したことによって、いい流れにならず、逆に点を取られてからも、危ないシーンがありました。それで途中からまた4バックに戻した。最終的に1−1だったんですけど、この結果の責任は自分にあります」
同点に追いつかれた後も、逆に相手にギャップを突かれて、SC相模原はピンチを招いた。指揮官も前述したように、3バックが機能しないと悟ったため、再び4バックに戻したが、ゲームの流れを今一度、引き寄せることはできなかった。
前半、流れをつかんでいただけに、追いつかれての引き分けは、敗戦のようなショックがある。指揮官も「選手たちに迷惑を掛けてしまったというのが率直なところです」と、自らの采配を悔やんだ。
|後半、3バックへ変更するが機能せずに失点
ところが、である。後半に入ると、つかんでいた主導権を相手に渡してしまう。高原が負傷したためハーフタイムで交代を余儀なくされたこともその一因だった。また、それに伴いDFフェア・モービーを投入して、前節同様、3バックにシステム変更したことも裏目に出た。3バックになったことで、マークが曖昧になる。両サイドの大森と森がより高い位置を取ることで攻撃に厚みが出たが、その一方で、2列目とウイングバック、ウイングバックとCBなど、至るところで距離が遠くなり、そのスペースを相手に使われるようになった。それが失点につながる。
64分だった。右サイドでFW益子義浩がフリーでボールを受けると、上がってきた髙瀨に縦パスが通る。そこから髙瀨にクロスを上げられると、走り込んできたMF高橋悠馬に頭で決められて同点に追いつかれてしまう。髙瀨にパスが通った時点でマークは揺さぶられ、クロスに走り込んできた高橋に対してもゴール前には人がいたにもかかわらず、フリーでフィニッシュさせてしまった。まさに3バックに変更したことによる責任転嫁が生んだ失点だった。辛島啓珠監督も認める。
「タカ(髙原直泰)がちょっと足に問題を抱えていて交代して。そこでモービーを入れて5バックにしたんですけど、4から5にシステム変更したことによって、いい流れにならず、逆に点を取られてからも、危ないシーンがありました。それで途中からまた4バックに戻した。最終的に1−1だったんですけど、この結果の責任は自分にあります」
同点に追いつかれた後も、逆に相手にギャップを突かれて、SC相模原はピンチを招いた。指揮官も前述したように、3バックが機能しないと悟ったため、再び4バックに戻したが、ゲームの流れを今一度、引き寄せることはできなかった。
前半、流れをつかんでいただけに、追いつかれての引き分けは、敗戦のようなショックがある。指揮官も「選手たちに迷惑を掛けてしまったというのが率直なところです」と、自らの采配を悔やんだ。
 |この引き分けをチームの分岐点とすることができるか
試合後、悔しそうな表情を浮かべスタジアムを後にする辛島監督の姿には、新たなる決意なようなものを見ることができた。何より、指揮官が自らの非を認める潔さには、清々しさすら感じる。就任から4試合で、つかんだ手応えや課題が浮き彫りになったのだろう。
そして何より、選手たちにも逞しさがある。曽我部にシステム変更による弊害があったかと尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「システム変更も少しは理由としてあるかもしれないですが、それ以上に、みんなも長くサッカーをやってきている中で、こうした状況は経験あるはず。みんな、やったことのないポジションではなかったと思うので。だからシステム変更というよりも、僕の中では完全に一人ひとりのエリアへの責任が、後半に関しては全くなくなり、引いて、怖がってしまった結果だと思います。システムというよりも個々が悪かった」
後半になり、高原が負傷したためピッチを去ると、攻撃でも高い位置でキープする選手がいなくなり、後方の上がりを促すことができなくなった。守備でも、チームとしての守備のスイッチを入れる役割がいなくなり、ボールの取りどころが分散し、連動性も曖昧になった。ここまで無得点の高原だが、いなくなって改めて存在感の大きさに気付かされる。ケガの状態は不明だが、彼がいないとき、チームとしてどのように戦っていくのか。誰が攻撃ではリーダーとなり、誰が守備ではチームを統率していくのか。チーム全体の底上げと、個々の責任感が問われていく。
1−1の引き分けではあったが、指揮官にとっても、選手たちにとっても、振り返ったとき、この試合がチームのターニングポイントだったと思える試合にすることができるか。それは次節の藤枝MYFC戦、そして4月19日にホームで行われるFC町田ゼルビアとの相武決戦で知ることができる。
|この引き分けをチームの分岐点とすることができるか
試合後、悔しそうな表情を浮かべスタジアムを後にする辛島監督の姿には、新たなる決意なようなものを見ることができた。何より、指揮官が自らの非を認める潔さには、清々しさすら感じる。就任から4試合で、つかんだ手応えや課題が浮き彫りになったのだろう。
そして何より、選手たちにも逞しさがある。曽我部にシステム変更による弊害があったかと尋ねると、次のような答えが返ってきた。
「システム変更も少しは理由としてあるかもしれないですが、それ以上に、みんなも長くサッカーをやってきている中で、こうした状況は経験あるはず。みんな、やったことのないポジションではなかったと思うので。だからシステム変更というよりも、僕の中では完全に一人ひとりのエリアへの責任が、後半に関しては全くなくなり、引いて、怖がってしまった結果だと思います。システムというよりも個々が悪かった」
後半になり、高原が負傷したためピッチを去ると、攻撃でも高い位置でキープする選手がいなくなり、後方の上がりを促すことができなくなった。守備でも、チームとしての守備のスイッチを入れる役割がいなくなり、ボールの取りどころが分散し、連動性も曖昧になった。ここまで無得点の高原だが、いなくなって改めて存在感の大きさに気付かされる。ケガの状態は不明だが、彼がいないとき、チームとしてどのように戦っていくのか。誰が攻撃ではリーダーとなり、誰が守備ではチームを統率していくのか。チーム全体の底上げと、個々の責任感が問われていく。
1−1の引き分けではあったが、指揮官にとっても、選手たちにとっても、振り返ったとき、この試合がチームのターニングポイントだったと思える試合にすることができるか。それは次節の藤枝MYFC戦、そして4月19日にホームで行われるFC町田ゼルビアとの相武決戦で知ることができる。