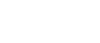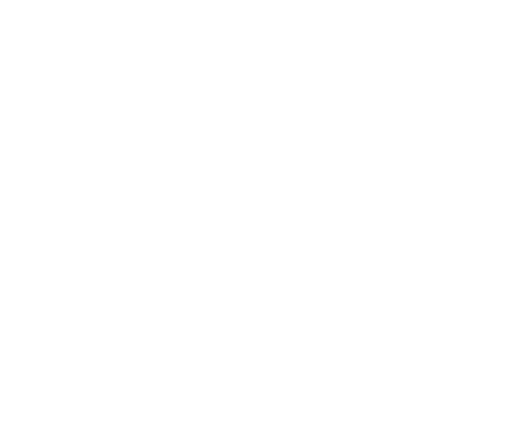2017明治安田生命J3リーグ第19節
2017.08.20 15:00KICKOFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原1−3セレッソ大阪U-23
[得点]相模原:53分徳永裕大/C大阪U-23:27分温井駿斗、28分、72分中島元彦
致命的なミスから喫した3失点に失望したが……。
試合が終わり、冷静に振り返れるようになるまで、かなりの時間を要した。正直、パソコンに向かってキーボードを叩いている今も、時折、堪えようのない感情が沸き起こってくる。それほどに、J3第19節で、セレッソ大阪U−23と戦ったSC相模原の試合内容には落胆した。クラブが目標としていた8200人には届かなかったものの、駆けつけてくれた今季最多6122人の観客も、遠からず苦い思いで帰路に就いたのだろうと考えると、なおさらやるせなくなる。
ただ、時間が経ち、客観的に試合を見られるようになったからか、異なる思考も巡ってきた。批判するのは簡単である。失点シーンをクローズアップし、ミスをあげつらえばいい……3トップの中央を担ったFW久保裕一も、2列目を務めたMF徳永裕大も、この試合を「自滅」と、ひと言で表現した。まさに喫した3失点は、すべて自分たちのミスが起因していた。
先制点を奪われたのは、前半27分だった。直前に得た右CKを跳ね返されたSC相模原は、カウンターを見舞われる。FW山根永遠のシュートこそ、懸命に戻った徳永の守備により逃れたが、これで与えたCKから失点する。ショートコーナーからクロスを上げられると、中途半端なクリアがDF温井駿斗のもとへ。豪快に左足を振り抜かれると、セットプレーからゴールを許した。
2失点目は、先制点を喫してわずか1分後だった。後方でボールをつなぐSC相模原は、右SBの辻尾真二が、GKの大畑拓也にバックパスを選択した。言ってしまえば、それは本当に何でもないパスだった。ところがGK大畑は、初先発の緊張もあったのか、この処理を見誤る。トラップが大きくなると、寄せていたFW中島元彦にボールをかっ攫われ、無人のゴールに流し込まれた。
後半27分に許した3失点目もお粗末だった。千明聖典が途中出場し、4−2−3−1にシステム変更していたSC相模原は、それまでアンカーを務めていた岡根直哉がCBに入っていた。その岡根からボランチの千明へと出した縦パスがずれたのである。これをMF荒木秀太に奪われると、カウンターから再び中島にゴールを許した。
1点目こそ微妙なマークのズレと対応の遅れから喫した失点だったが、2点目、3点目は明かなミスによるものだった。それ以外にも、前半から高い位置でプレスを掛けられては奪われたり、中央で横パスをかっ攫われたりと、危険なエリアでボールを失う場面が、これまでの試合以上に際立った。
 新たなチャレンジがミスを引き起こす結果に
新たなチャレンジがミスを引き起こす結果に
では、なぜ、SC相模原はこうしたイージーとも安易とも言える失点を、再三、引き起こしてしまったのか。そこに筆者が、時間とともに異なる感情が芽生えてきた理由もある。それを説明するには、安永聡太郎監督のコメントを引用しよう。
「(失点は)与えたCKからと、GKのミスパスから。ただ、これはリーグ前半戦であったならば、起きていなかったであろう失点ですよね」
中断前までのSC相模原は、まずFWに浮き球ないしは縦パスを当て、その落としを拾い、サイドに展開することで、攻撃を組み立ててきた。守備を強く意識したその戦い方は、失点数が示していたように、堅守というチームの基軸になっていた。その一方で、サイドに偏った攻撃は迫力を欠き、得点力が著しく乏しかった。それは中断前までの18試合で、4勝しか挙げられず、13得点しか奪えなかった結果が示してもいる。
だからこそ、安永監督は、この中断期間中に、新たなチャレンジをした。大改革とも言えるその挑戦は、簡潔に言えば、ポゼッションサッカーへの転換である。再び安永監督の言葉を借りる。
「僕個人としても、どちらかと言えば、しっかりとボールを握って、自ら運び出して得点を取るサッカーをしたい。それがすべてうまくいくわけではないですけど、勝つために、やっぱり、その部分の確率を上げていきたいという思いは強いですよね」
点を取るために、試合を支配するために、SC相模原は、これまでの蹴って拾ってというシンプルなスタイルから、大きな脱却を図ろうとした。喫した3失点は、そこにトライした結果でもある。
1−3で敗れたからと言って、すべてが機能しなかったわけではない。再び安永監督である。
「今までにない形もあった。サイドの高い位置を、狙いを持って取りにいけるようになった。そこからボールを戻してしまうのが悪いとは言わないですけど、せっかく高い位置を取れたのに、そこからペナ脇(ペナルティーエリアの脇)を取りに行こうとする選手がいなかった。そこをどう取りにいくのか。(トレーニングから)積極的にやっていかなければいけないというのは選手たちも感じたと思う」
 「2」と「4」を取れればゴールは生まれる
「2」と「4」を取れればゴールは生まれる
ひとつその狙いを説明すれば、クロスを入れる位置である。相手ゴール前を縦に5分割して、右から「1」〜「5」のエリアを設定したとする。これまでのSC相模原は、大外となる「1」か「5」からしかクロスを上げられていなかった。それではゴールまでの距離は遠く、なかなかフィニッシュにはつながらない。得点につなげるには、「3」を中央としたところの、「2」ないしは「4」のエリアから、クロスなりラストパスを入れる必要があった。詳細は省くが、これは現代サッカーにおいてゴールにつながるアシストを数値化したデータとしても如実に表れている。
まさに、この試合で奪った唯一の得点がその形からだった。後半8分、途中出場した呉大陸がドリブルで仕掛けると、ペナルティーエリアのライン上まで切り込む。まさに「4」のエリアを取ったのである。そこから呉は折り返すと、走り込んだ岡根がスルー。遅れて飛び込んで来た徳永が右足を振り抜いた。徳永が得点シーンを振り返る。
「後半からダイムくん(呉)が入ったので左サイドはどんどん突破していけるだろうと思った。だから、ダイムくんのラストパスにしっかりと入っていけるように準備していた。得点シーンは、遅れて入りましたけど、オカさん(岡根)がしっかり見ていてくれて、スルーしてくれた。その結果、自分はドフリーになったので、あとはふかさないようにと思って枠に蹴りました。ただ、90分を通してチームとしてやりたいことができたのは、得点を奪った前後だけだったので、その時間帯をもっと増やしていかなければならない。まずはビルドアップするところでボールを取られないようにしないと。奪われてはいけない位置があるので、そのゾーンではしっかりプレーできるようにしたい」
ボールを握る、自ら持ち運ぶ試みにより、水を得た魚のように輝きを取り戻したのが、後半頭から途中出場した呉である。
「俺っぽい形からの得点だったかなって思います。ようやく持ち味が出せるようになってきた。ちょっとずつですけど、自分のやるべきことが分かってきて、チームにもそれが浸透してきているかなって思う。ただ、肝心の試合に負けてしまっていますからね。もっと突破できたし、点も取れたと思う。少しずつ手応えは感じられているので、そのあとちょっとの部分を突き詰めていきたい。俺としては、中と外のバリエーションを自分で見つけて、相手の嫌がる感覚を探っていきたい」
中断期間中にトライしてきたボールを保持する、ボールを運んで仕掛けるというプレーにトライした結果、チームはミスを誘発した。これまでは、縦一辺倒だったのに対して、横パスややり直すためのバックパスも増えるため、少しでもずれれば、致命的なミスにつながる。また、横パスをするために、チーム全体が前向きにセットできなくなり、戻った選手が後ろ向きになっていることで、そこでミスが生じれば、相手に好機を作られることにもなった。その怖さは、危うさは、ピッチに立った選手たちが何より分かっていることだろう。
 選手たちの言葉を聞き、落胆から希望を抱いた
選手たちの言葉を聞き、落胆から希望を抱いた
足もとの技術に長けていることから、先発に抜擢されたGK大畑は、誰よりもそれを痛感している。あの致命的なミスは、彼のキャリアにおいても、サッカー人生においても、初めてのことだった。
「本当にあのワンプレーがすべてですよね。いくら自分の武器を出そうとしても、それでゲームを壊してしまっては……本当に申し訳ないですよね。そこがGKの責任の重さですし、ミスした後、自分で得点を奪って取り返せるポジションではないので……。その重さというのを、今日、僕自身は前向きな言葉で言えば、本当に勉強させてもらいました。その表現でいいのか分からないですけど……本当に見に来てくれた人には申し訳ないです」
観客に詫びるように何度も、何度も、大畑は謝った。すぐには切り替えられないと潔く認めるほど、平静を装いつつ、悔しさを噛みしめていた。
その言葉を聞いたからこそ、筆者は異なる感情を抱いたのである。繰り返すが、批判するのは簡単である。ミスを指摘し、並べればいい。ただ、それは誰よりもピッチにいる選手たちが体感したはずである。得点を奪うには、ボールを保持するには、すべてにおいて質を高めなければならないと。指揮官は言った。
「この1回のチームとしての不出来で、やっぱりやめたになってしまうと、この(中断の)1カ月は何だったんだということになってしまう。だから、やり方は、戦い方は変えるつもりはありません」
ならば、その答えが出るのを信じて見届けるまでである。そう思わせてくれたのは、指揮官と、それを体現しようとする選手たちの言葉だ。
 2017明治安田生命J3リーグ第19節
2017.08.20 15:00KICKOFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原1−3セレッソ大阪U-23
[得点]相模原:53分徳永裕大/C大阪U-23:27分温井駿斗、28分、72分中島元彦
致命的なミスから喫した3失点に失望したが……。
試合が終わり、冷静に振り返れるようになるまで、かなりの時間を要した。正直、パソコンに向かってキーボードを叩いている今も、時折、堪えようのない感情が沸き起こってくる。それほどに、J3第19節で、セレッソ大阪U−23と戦ったSC相模原の試合内容には落胆した。クラブが目標としていた8200人には届かなかったものの、駆けつけてくれた今季最多6122人の観客も、遠からず苦い思いで帰路に就いたのだろうと考えると、なおさらやるせなくなる。
ただ、時間が経ち、客観的に試合を見られるようになったからか、異なる思考も巡ってきた。批判するのは簡単である。失点シーンをクローズアップし、ミスをあげつらえばいい……3トップの中央を担ったFW久保裕一も、2列目を務めたMF徳永裕大も、この試合を「自滅」と、ひと言で表現した。まさに喫した3失点は、すべて自分たちのミスが起因していた。
先制点を奪われたのは、前半27分だった。直前に得た右CKを跳ね返されたSC相模原は、カウンターを見舞われる。FW山根永遠のシュートこそ、懸命に戻った徳永の守備により逃れたが、これで与えたCKから失点する。ショートコーナーからクロスを上げられると、中途半端なクリアがDF温井駿斗のもとへ。豪快に左足を振り抜かれると、セットプレーからゴールを許した。
2失点目は、先制点を喫してわずか1分後だった。後方でボールをつなぐSC相模原は、右SBの辻尾真二が、GKの大畑拓也にバックパスを選択した。言ってしまえば、それは本当に何でもないパスだった。ところがGK大畑は、初先発の緊張もあったのか、この処理を見誤る。トラップが大きくなると、寄せていたFW中島元彦にボールをかっ攫われ、無人のゴールに流し込まれた。
後半27分に許した3失点目もお粗末だった。千明聖典が途中出場し、4−2−3−1にシステム変更していたSC相模原は、それまでアンカーを務めていた岡根直哉がCBに入っていた。その岡根からボランチの千明へと出した縦パスがずれたのである。これをMF荒木秀太に奪われると、カウンターから再び中島にゴールを許した。
1点目こそ微妙なマークのズレと対応の遅れから喫した失点だったが、2点目、3点目は明かなミスによるものだった。それ以外にも、前半から高い位置でプレスを掛けられては奪われたり、中央で横パスをかっ攫われたりと、危険なエリアでボールを失う場面が、これまでの試合以上に際立った。
2017明治安田生命J3リーグ第19節
2017.08.20 15:00KICKOFF@相模原ギオンスタジアム
SC相模原1−3セレッソ大阪U-23
[得点]相模原:53分徳永裕大/C大阪U-23:27分温井駿斗、28分、72分中島元彦
致命的なミスから喫した3失点に失望したが……。
試合が終わり、冷静に振り返れるようになるまで、かなりの時間を要した。正直、パソコンに向かってキーボードを叩いている今も、時折、堪えようのない感情が沸き起こってくる。それほどに、J3第19節で、セレッソ大阪U−23と戦ったSC相模原の試合内容には落胆した。クラブが目標としていた8200人には届かなかったものの、駆けつけてくれた今季最多6122人の観客も、遠からず苦い思いで帰路に就いたのだろうと考えると、なおさらやるせなくなる。
ただ、時間が経ち、客観的に試合を見られるようになったからか、異なる思考も巡ってきた。批判するのは簡単である。失点シーンをクローズアップし、ミスをあげつらえばいい……3トップの中央を担ったFW久保裕一も、2列目を務めたMF徳永裕大も、この試合を「自滅」と、ひと言で表現した。まさに喫した3失点は、すべて自分たちのミスが起因していた。
先制点を奪われたのは、前半27分だった。直前に得た右CKを跳ね返されたSC相模原は、カウンターを見舞われる。FW山根永遠のシュートこそ、懸命に戻った徳永の守備により逃れたが、これで与えたCKから失点する。ショートコーナーからクロスを上げられると、中途半端なクリアがDF温井駿斗のもとへ。豪快に左足を振り抜かれると、セットプレーからゴールを許した。
2失点目は、先制点を喫してわずか1分後だった。後方でボールをつなぐSC相模原は、右SBの辻尾真二が、GKの大畑拓也にバックパスを選択した。言ってしまえば、それは本当に何でもないパスだった。ところがGK大畑は、初先発の緊張もあったのか、この処理を見誤る。トラップが大きくなると、寄せていたFW中島元彦にボールをかっ攫われ、無人のゴールに流し込まれた。
後半27分に許した3失点目もお粗末だった。千明聖典が途中出場し、4−2−3−1にシステム変更していたSC相模原は、それまでアンカーを務めていた岡根直哉がCBに入っていた。その岡根からボランチの千明へと出した縦パスがずれたのである。これをMF荒木秀太に奪われると、カウンターから再び中島にゴールを許した。
1点目こそ微妙なマークのズレと対応の遅れから喫した失点だったが、2点目、3点目は明かなミスによるものだった。それ以外にも、前半から高い位置でプレスを掛けられては奪われたり、中央で横パスをかっ攫われたりと、危険なエリアでボールを失う場面が、これまでの試合以上に際立った。
 新たなチャレンジがミスを引き起こす結果に
では、なぜ、SC相模原はこうしたイージーとも安易とも言える失点を、再三、引き起こしてしまったのか。そこに筆者が、時間とともに異なる感情が芽生えてきた理由もある。それを説明するには、安永聡太郎監督のコメントを引用しよう。
「(失点は)与えたCKからと、GKのミスパスから。ただ、これはリーグ前半戦であったならば、起きていなかったであろう失点ですよね」
中断前までのSC相模原は、まずFWに浮き球ないしは縦パスを当て、その落としを拾い、サイドに展開することで、攻撃を組み立ててきた。守備を強く意識したその戦い方は、失点数が示していたように、堅守というチームの基軸になっていた。その一方で、サイドに偏った攻撃は迫力を欠き、得点力が著しく乏しかった。それは中断前までの18試合で、4勝しか挙げられず、13得点しか奪えなかった結果が示してもいる。
だからこそ、安永監督は、この中断期間中に、新たなチャレンジをした。大改革とも言えるその挑戦は、簡潔に言えば、ポゼッションサッカーへの転換である。再び安永監督の言葉を借りる。
「僕個人としても、どちらかと言えば、しっかりとボールを握って、自ら運び出して得点を取るサッカーをしたい。それがすべてうまくいくわけではないですけど、勝つために、やっぱり、その部分の確率を上げていきたいという思いは強いですよね」
点を取るために、試合を支配するために、SC相模原は、これまでの蹴って拾ってというシンプルなスタイルから、大きな脱却を図ろうとした。喫した3失点は、そこにトライした結果でもある。
1−3で敗れたからと言って、すべてが機能しなかったわけではない。再び安永監督である。
「今までにない形もあった。サイドの高い位置を、狙いを持って取りにいけるようになった。そこからボールを戻してしまうのが悪いとは言わないですけど、せっかく高い位置を取れたのに、そこからペナ脇(ペナルティーエリアの脇)を取りに行こうとする選手がいなかった。そこをどう取りにいくのか。(トレーニングから)積極的にやっていかなければいけないというのは選手たちも感じたと思う」
新たなチャレンジがミスを引き起こす結果に
では、なぜ、SC相模原はこうしたイージーとも安易とも言える失点を、再三、引き起こしてしまったのか。そこに筆者が、時間とともに異なる感情が芽生えてきた理由もある。それを説明するには、安永聡太郎監督のコメントを引用しよう。
「(失点は)与えたCKからと、GKのミスパスから。ただ、これはリーグ前半戦であったならば、起きていなかったであろう失点ですよね」
中断前までのSC相模原は、まずFWに浮き球ないしは縦パスを当て、その落としを拾い、サイドに展開することで、攻撃を組み立ててきた。守備を強く意識したその戦い方は、失点数が示していたように、堅守というチームの基軸になっていた。その一方で、サイドに偏った攻撃は迫力を欠き、得点力が著しく乏しかった。それは中断前までの18試合で、4勝しか挙げられず、13得点しか奪えなかった結果が示してもいる。
だからこそ、安永監督は、この中断期間中に、新たなチャレンジをした。大改革とも言えるその挑戦は、簡潔に言えば、ポゼッションサッカーへの転換である。再び安永監督の言葉を借りる。
「僕個人としても、どちらかと言えば、しっかりとボールを握って、自ら運び出して得点を取るサッカーをしたい。それがすべてうまくいくわけではないですけど、勝つために、やっぱり、その部分の確率を上げていきたいという思いは強いですよね」
点を取るために、試合を支配するために、SC相模原は、これまでの蹴って拾ってというシンプルなスタイルから、大きな脱却を図ろうとした。喫した3失点は、そこにトライした結果でもある。
1−3で敗れたからと言って、すべてが機能しなかったわけではない。再び安永監督である。
「今までにない形もあった。サイドの高い位置を、狙いを持って取りにいけるようになった。そこからボールを戻してしまうのが悪いとは言わないですけど、せっかく高い位置を取れたのに、そこからペナ脇(ペナルティーエリアの脇)を取りに行こうとする選手がいなかった。そこをどう取りにいくのか。(トレーニングから)積極的にやっていかなければいけないというのは選手たちも感じたと思う」
 「2」と「4」を取れればゴールは生まれる
ひとつその狙いを説明すれば、クロスを入れる位置である。相手ゴール前を縦に5分割して、右から「1」〜「5」のエリアを設定したとする。これまでのSC相模原は、大外となる「1」か「5」からしかクロスを上げられていなかった。それではゴールまでの距離は遠く、なかなかフィニッシュにはつながらない。得点につなげるには、「3」を中央としたところの、「2」ないしは「4」のエリアから、クロスなりラストパスを入れる必要があった。詳細は省くが、これは現代サッカーにおいてゴールにつながるアシストを数値化したデータとしても如実に表れている。
まさに、この試合で奪った唯一の得点がその形からだった。後半8分、途中出場した呉大陸がドリブルで仕掛けると、ペナルティーエリアのライン上まで切り込む。まさに「4」のエリアを取ったのである。そこから呉は折り返すと、走り込んだ岡根がスルー。遅れて飛び込んで来た徳永が右足を振り抜いた。徳永が得点シーンを振り返る。
「後半からダイムくん(呉)が入ったので左サイドはどんどん突破していけるだろうと思った。だから、ダイムくんのラストパスにしっかりと入っていけるように準備していた。得点シーンは、遅れて入りましたけど、オカさん(岡根)がしっかり見ていてくれて、スルーしてくれた。その結果、自分はドフリーになったので、あとはふかさないようにと思って枠に蹴りました。ただ、90分を通してチームとしてやりたいことができたのは、得点を奪った前後だけだったので、その時間帯をもっと増やしていかなければならない。まずはビルドアップするところでボールを取られないようにしないと。奪われてはいけない位置があるので、そのゾーンではしっかりプレーできるようにしたい」
ボールを握る、自ら持ち運ぶ試みにより、水を得た魚のように輝きを取り戻したのが、後半頭から途中出場した呉である。
「俺っぽい形からの得点だったかなって思います。ようやく持ち味が出せるようになってきた。ちょっとずつですけど、自分のやるべきことが分かってきて、チームにもそれが浸透してきているかなって思う。ただ、肝心の試合に負けてしまっていますからね。もっと突破できたし、点も取れたと思う。少しずつ手応えは感じられているので、そのあとちょっとの部分を突き詰めていきたい。俺としては、中と外のバリエーションを自分で見つけて、相手の嫌がる感覚を探っていきたい」
中断期間中にトライしてきたボールを保持する、ボールを運んで仕掛けるというプレーにトライした結果、チームはミスを誘発した。これまでは、縦一辺倒だったのに対して、横パスややり直すためのバックパスも増えるため、少しでもずれれば、致命的なミスにつながる。また、横パスをするために、チーム全体が前向きにセットできなくなり、戻った選手が後ろ向きになっていることで、そこでミスが生じれば、相手に好機を作られることにもなった。その怖さは、危うさは、ピッチに立った選手たちが何より分かっていることだろう。
「2」と「4」を取れればゴールは生まれる
ひとつその狙いを説明すれば、クロスを入れる位置である。相手ゴール前を縦に5分割して、右から「1」〜「5」のエリアを設定したとする。これまでのSC相模原は、大外となる「1」か「5」からしかクロスを上げられていなかった。それではゴールまでの距離は遠く、なかなかフィニッシュにはつながらない。得点につなげるには、「3」を中央としたところの、「2」ないしは「4」のエリアから、クロスなりラストパスを入れる必要があった。詳細は省くが、これは現代サッカーにおいてゴールにつながるアシストを数値化したデータとしても如実に表れている。
まさに、この試合で奪った唯一の得点がその形からだった。後半8分、途中出場した呉大陸がドリブルで仕掛けると、ペナルティーエリアのライン上まで切り込む。まさに「4」のエリアを取ったのである。そこから呉は折り返すと、走り込んだ岡根がスルー。遅れて飛び込んで来た徳永が右足を振り抜いた。徳永が得点シーンを振り返る。
「後半からダイムくん(呉)が入ったので左サイドはどんどん突破していけるだろうと思った。だから、ダイムくんのラストパスにしっかりと入っていけるように準備していた。得点シーンは、遅れて入りましたけど、オカさん(岡根)がしっかり見ていてくれて、スルーしてくれた。その結果、自分はドフリーになったので、あとはふかさないようにと思って枠に蹴りました。ただ、90分を通してチームとしてやりたいことができたのは、得点を奪った前後だけだったので、その時間帯をもっと増やしていかなければならない。まずはビルドアップするところでボールを取られないようにしないと。奪われてはいけない位置があるので、そのゾーンではしっかりプレーできるようにしたい」
ボールを握る、自ら持ち運ぶ試みにより、水を得た魚のように輝きを取り戻したのが、後半頭から途中出場した呉である。
「俺っぽい形からの得点だったかなって思います。ようやく持ち味が出せるようになってきた。ちょっとずつですけど、自分のやるべきことが分かってきて、チームにもそれが浸透してきているかなって思う。ただ、肝心の試合に負けてしまっていますからね。もっと突破できたし、点も取れたと思う。少しずつ手応えは感じられているので、そのあとちょっとの部分を突き詰めていきたい。俺としては、中と外のバリエーションを自分で見つけて、相手の嫌がる感覚を探っていきたい」
中断期間中にトライしてきたボールを保持する、ボールを運んで仕掛けるというプレーにトライした結果、チームはミスを誘発した。これまでは、縦一辺倒だったのに対して、横パスややり直すためのバックパスも増えるため、少しでもずれれば、致命的なミスにつながる。また、横パスをするために、チーム全体が前向きにセットできなくなり、戻った選手が後ろ向きになっていることで、そこでミスが生じれば、相手に好機を作られることにもなった。その怖さは、危うさは、ピッチに立った選手たちが何より分かっていることだろう。
 選手たちの言葉を聞き、落胆から希望を抱いた
足もとの技術に長けていることから、先発に抜擢されたGK大畑は、誰よりもそれを痛感している。あの致命的なミスは、彼のキャリアにおいても、サッカー人生においても、初めてのことだった。
「本当にあのワンプレーがすべてですよね。いくら自分の武器を出そうとしても、それでゲームを壊してしまっては……本当に申し訳ないですよね。そこがGKの責任の重さですし、ミスした後、自分で得点を奪って取り返せるポジションではないので……。その重さというのを、今日、僕自身は前向きな言葉で言えば、本当に勉強させてもらいました。その表現でいいのか分からないですけど……本当に見に来てくれた人には申し訳ないです」
観客に詫びるように何度も、何度も、大畑は謝った。すぐには切り替えられないと潔く認めるほど、平静を装いつつ、悔しさを噛みしめていた。
その言葉を聞いたからこそ、筆者は異なる感情を抱いたのである。繰り返すが、批判するのは簡単である。ミスを指摘し、並べればいい。ただ、それは誰よりもピッチにいる選手たちが体感したはずである。得点を奪うには、ボールを保持するには、すべてにおいて質を高めなければならないと。指揮官は言った。
「この1回のチームとしての不出来で、やっぱりやめたになってしまうと、この(中断の)1カ月は何だったんだということになってしまう。だから、やり方は、戦い方は変えるつもりはありません」
ならば、その答えが出るのを信じて見届けるまでである。そう思わせてくれたのは、指揮官と、それを体現しようとする選手たちの言葉だ。
選手たちの言葉を聞き、落胆から希望を抱いた
足もとの技術に長けていることから、先発に抜擢されたGK大畑は、誰よりもそれを痛感している。あの致命的なミスは、彼のキャリアにおいても、サッカー人生においても、初めてのことだった。
「本当にあのワンプレーがすべてですよね。いくら自分の武器を出そうとしても、それでゲームを壊してしまっては……本当に申し訳ないですよね。そこがGKの責任の重さですし、ミスした後、自分で得点を奪って取り返せるポジションではないので……。その重さというのを、今日、僕自身は前向きな言葉で言えば、本当に勉強させてもらいました。その表現でいいのか分からないですけど……本当に見に来てくれた人には申し訳ないです」
観客に詫びるように何度も、何度も、大畑は謝った。すぐには切り替えられないと潔く認めるほど、平静を装いつつ、悔しさを噛みしめていた。
その言葉を聞いたからこそ、筆者は異なる感情を抱いたのである。繰り返すが、批判するのは簡単である。ミスを指摘し、並べればいい。ただ、それは誰よりもピッチにいる選手たちが体感したはずである。得点を奪うには、ボールを保持するには、すべてにおいて質を高めなければならないと。指揮官は言った。
「この1回のチームとしての不出来で、やっぱりやめたになってしまうと、この(中断の)1カ月は何だったんだということになってしまう。だから、やり方は、戦い方は変えるつもりはありません」
ならば、その答えが出るのを信じて見届けるまでである。そう思わせてくれたのは、指揮官と、それを体現しようとする選手たちの言葉だ。