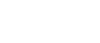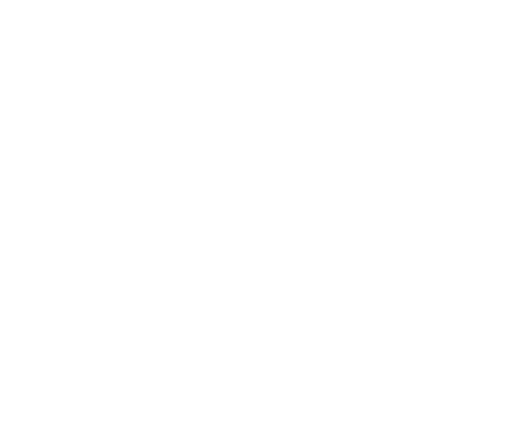J3リーグ第20節を終えて8勝6分6敗の7位と燻っている成績に加え、天皇杯神奈川県予選準決勝で敗退したことにより、8月18日、指揮を執っていた薩川了洋前監督がクラブに辞任を申し出た。
後任として、急遽SC相模原の指揮を託されたのは安永聡太郎だった。監督経験はなく、指揮官としての手腕は未知数である。ただ、その胸にはスペインで学んだ確固たる哲学と、解説者として活動する間もぶれることのなかった揺るぎない信念がある。
今シーズンのJ3リーグも残り10試合——安永新監督はいかなるチームを築こうとしているのか。そのコンセプトを聞く前に、まずは突然の監督就任を引き受けた決意と背景に耳を傾ける。
監督就任はほぼ即答で引き受けた
——SC相模原の監督就任が決まったのが8月20日。シーズン途中での監督就任ですが、自身にとって初の監督業でもあります。率直にどのような思いで引き受けたのでしょうか。
「ずっと監督としてチームを率いてみたいとは思っていたんですよね。一度、指導者の勉強を兼ねてスペインに行き、セグンダB(3部)のCDギフェロというクラブでコーチ契約をしてもらえたんです。ただ、クラブの財政が苦しく、無報酬ならば、という条件でした。ルベン・デ・ラ・バレーラという素晴らしい監督にも出会え、そこで指導者としての一歩を踏み出したいなと思っていたのですが、やっぱり、家族のことを考えると、さすがに無茶はできなかった。それで、しぶしぶ日本に帰ってきたのですが、帰国当初は凹みましたよね。それまで、自分の中に『これだ』というサッカーへの理論はありましたが、いかんせん、現場で指導してみなければ分からないことも多かった。だからこそ、どうせ指導するならば、自分が感銘を受けているスペインで始めたかった。本当にそう思えるほど、CDギフェロで出会ったルベンという監督とは、戦術的な話がたくさんできる間柄だったんです」
——スペインで指導者としてスタートを切るという夢を断念して帰国してからは、再びサッカー解説者をされていましたよね。
「だから、オレは指導者としても“できる”というところを見せたくて、ついつい解説のときにも、自分の理論を口にしていたんですよね。正直、自分にとって、解説の仕事をしているときは、指導者としてのアピールの場だとも考えていたんです。だから、オレはここまで見ているぞ、ここまで分かっているぞというのをついつい言ってしまう。そのせいで視聴者の中には、言い過ぎだろうとか、上から目線だと感じた人もいたでしょうね」
——確かに解説をしているときの印象は、他とは異なるというか色が濃かったというか、具体的に自分の考えを言葉として表現する人だなというイメージがありました。特に言葉をすごく大切にしているなと。
「自分でも言葉の重要性、伝えるということはかなり意識していますね。というのも、現役を引退してから約10年間、JFAこころのプロジェクト『ユメセン』に携わらせてもらいました。そこでは単純計算しただけでも、3万人近い子どもたち、1500人くらいの担任の先生、そして、300人を越える夢先生と一緒に活動し、触れ合ってきました。その活動を通して学んだことが、それはもう、大きかったんですよね。言葉の伝え方、当たり前だけど、それぞれの考え方の違い、また他競技の選手たちからは、個人種目と団体種目における考え方の違いについても勉強させてもらった。特にサッカー選手とは違って、オリンピック選手は365日×4年分の1(1日)にピークを持っていかなければならない。その難しさたるや……オリンピックに出場する過程での苦悩……葛藤を聞かせてもらった。その上で、みんな、4年後を見るのではなく、1日、1日を見て取り組むことの重要性を語っていました。今の自分に何ができるのかということの積み重ねが、4年後の1日につながると」
——サッカー人、指導者としての安永聡太郎だけでなく、人間・安永聡太郎を形成する上でも、JFAこころのプロジェクトで得たことは大きかったんですね。
「本当にそうですね。他には、学校によっても、担任の先生によっても、子どもたちによってもクラスの雰囲気は違ったので、そのときどきで、伝え方を変えなければならなかった。その都度、その都度、雰囲気を感じ取ってアプローチの方法を変えなければ、こちらのメッセージをきちんと伝えることはできないんです。そこは、まさにサッカーの指導にも通じるところがあると思っています。本当に、JFAこころのプロジェクトに10年間携われたことは、今後の自分の指導に活きてくると、自負しています。あの経験は必ず財産になると」
——他にもCPサッカー(脳性麻痺7人制サッカー)の日本代表監督として指導にも当たっていましたよね。
「あの経験も本当に素晴らしい経験になりました。それまでCPサッカーがどんなものかは知らなかったのですが、選手たちと触れ合う中で、彼らのことを理解していきました。CPサッカーはGKを含めた7人制なのですが、フィールドの6人をどう配置して戦うか。対戦相手もいる中で、絶対にやられてはいけないところを伝え、それを選手たちが実行してくれた。同時に強く言うことで意識させすぎてしまうことの難しさも知った。個人としては勝負の世界に身を置いていることが、たまらなく充実していて、大会が終わったときには少し抜け殻になっていたんですよね。また、指導者としてその機微を味わいたいなと。そう思っていたときに、SC相模原から監督就任の話をもらった。短期間で、いろいろと考えましたけど、やるしかないだろうと思い、ほぼ即答で引き受けました」
 戦えない、走れない…攻守の切り替えが遅い。
戦えない、走れない…攻守の切り替えが遅い。
SC相模原の監督就任を打診され、実際に指導に当たるまでには、わずかな時間しかなかった。限られた時間の中で見たSC相模原の試合で、安永監督が感じた課題とは何だったのか。
自身も「細かくて、しつこい」と笑うように、練習では具体的な指示がいくつも飛んでいる。常に大声を張り上げ、選手たちに訴えかけているため、のど飴が必需品になっているという。分析した課題であり、そのアプローチ方法を知れば、新たなるスタートを切るSC相模原のコンセプトが見えてくる。
——指導前に試合の映像を見たそうですが、そこで感じたチームへの課題とは?
「まず感じたのは、戦えない、走れない……攻守の切り替えが遅いというところでしたね。練習をはじめて、すぐにそれを選手たちにも言いました。走れないのは、純粋に走れないのか、それとも走りたいけど走り方が分からないのか。そこは映像だけでは判断できず、直接、指導する中で確認したいと思っていました」
——実際に練習で指導してみて、どっちだったんですか?
「両方でしたね。実際、単純に走れていないところもありました。一方で、走り方を指示してみても、走ろうとするけど、その走り方が分かっていなかった。例えば、サイドの選手がどこにポジションを取っているのか、ボールを動かしているときに自分は何をしたらいいのかが分かっていなかった。特に顕著だったのは、ボールを動かすことにこだわるがゆえに、みんながボールを受けに戻ってくるため、すべてのプレーが後ろ向きになっていたんですよね。後ろ向きにプレーするから、相手は前向きにプレッシャーを掛けられる。そこで自分たちは苦しくなるから、前に蹴りますよね。でも、そこでも後ろ向きに戻ってきているからセカンドボールを拾われてしまう。その繰り返しだったんです。だから、選手たちには、基本的に後ろ向きでボールを受けるなということを言いました。前、もしくは横を向いた状態でボールを受けられるようにしようと。ポゼッションするけれども、まずはポジションプレーなんですよね。正確なポジションを各々が取ることで、ポゼッションしているところでは、相手に圧を掛けさせないようにできる」
——サッカーはゴールを奪うスポーツです。そのためにも、前向きでプレーする意識は重要かもしれませんね。
「正確なポジションを取っていても、相手が無理にプレスを掛けてきたのであれば、オレはそのボールを蹴ってもいいと思っています。そのときはどこかで必ず数的優位か数的同数の状況が作れているはずだから。そこで相手とのボールの奪い合いが起こったとしても、周りや相手には偶然に見えるかもしれないけど、オレの考え方としては、それは必然になる。チームのコンセプトとしては、偶然を必然に変える作業をどれだけできるか。うちのチームにおいて、『ラッキーだったね』というプレーはないようにしたい。プレーのひとつひとつが起こるべくして起きたプレーになる。そして、そのためにチームとしての共通認識というものが重要になってくる」

——偶然を必然に変える。それを具現化するために目指すサッカーとは?
「我々はプロだから、まず試合に勝たなければならないですよね。大前提として、勝つために何ができるかというのがある。だから、対戦する時点での自分たちと、相手との力量によっても戦い方は変わってくると思っています。相手のほうが強く、前からプレッシャーを掛けてくるチームに対して、今のチームの現状で後ろからつなげば、相手の守備にハメられてしまう確率は高い。それならば、極端な話、オレは蹴るサッカーを選択する。だから、どういうサッカーを目指しますかと聞かれると、答えられないかもしれない(笑)」
——こちらから聞いておいて、あれですが、ちょっと分かる気がします。日本は多くのチームが自分たちのサッカー、自分たちのサッカーと提唱しすぎる傾向がありますよね。
「ですよね? よくバルセロナみたいなサッカーを目指すと言う話を聞きますけど、純粋にすごいなと思ってしまうところがあります。バルセロナはバルセロナだから、あの戦い方を貫ける。そこには(リオネル・)メッシがいて、何十億円もの資金を投じて、より目指すサッカーを強固にして、具体化できる。世界を見ても、それを貫けているのはバルセロナくらい。でも、オレはどの試合も勝ちたいから、まずは相手を分析して、この相手には何をすれば一番、勝率が上がるかを考える。どうすれば効果的なのかを考えた上でメンバーも選び、変えていくつもりです。ただし、チームとして統一感のない試合をするつもりはありません。ピッチに立った選手がそれぞれ11km近くをバラバラに走るのではなく、直線(前向き)に走ることで、総合的に120kmにしたい。もちろん、試合中にそのすべての状況を作るのが難しいことは分かっています。でも、ぶれずにやっていきたいなと」
——結果を求めるために、相手によって戦い方を変えていくということですよね?
「そうですね。育成年代であれば別ですが、プロである以上、結果を追い求めていきたい。SC相模原でも、ボールをつなぐようなサッカーをしたいですが、先ほども言ったように、苦しければ蹴ってもいい。ただし! それには必ず、人が降りてくるようにしたい。蹴りっぱなしにならないこと。蹴ったらラインを上げて、セカンドボールを拾う準備をする。攻められている同サイドに必ずFWが降りてくる。それによって同サイドにクリアした場合は、ボールを拾える可能性がゼロではなくなっているわけですからね。相手よりも実力があると判断すればつなぎます。そのときは、1週間、ボールをつないで相手を外す、崩す練習を取り入れていく。前線には狭いエリアでつなげる選手を配置しなければならないから、当然、そのときはメンバーも変わってきますよね。要するに、相手の長所と短所をしっかりと見極めて、戦っていきたい。そのためにみっちり練習して、選手たちには必死についてきてもらう代わりに、試合で起こったことの責任はすべてオレにあると思っています。選手たちには、その上で、個々に責任と自由があって、チームプレーにおいての責任は与えます。ただ、それを判断するのも選手たち自身。チームとしてやろうとしていることと違う選択をして失敗したときには、その代わり責任は取ってもらうよと。それはメンバーを変えることかもしれないし、途中交代という形になるかもしれないですけどね。ただ、監督が言うことだけをやっているだけでは、サッカーは面白くないですよね。だから、すべてにおいて状況判断が大事なんです。ピッチ全体を3つのエリア(ディフェンディングサード、ミドルサード、アタッキングサード)に分けた場合、ここ(ミドルサード)まではチームとしての約束ごとがある。でも、ここ(アタッキングサード)まで来たら、選手たちの自由だよと思っている。そこに到達したときには、それまで制限されていたわけだから、自分の個性を思いっ切り解放してほしいなと思っています」
——自分自身でも試行錯誤しながらの日々だとは思いますが、練習を見ていても充実していることは感じます。
「この方向性が良いのか悪いのかも含めて、正直、経験がないので判断はできません(笑)。でも、誰もが、そうであるように経験はやらなければ積むことはできない。本当に日々、良い勉強をさせてもらっていると思っていますし、クラブには感謝しています。選手には迷惑を掛けているかもしれないですが、そこはお互いにリスペクトしてやっていければと思っています。毎試合、勝利のため、勝つということにこだわってやっていきたい。それで90分が終わったときに、ピッチに倒れ込む選手がどれだけいるか。10試合終わったときには、ピッチにいる全員がそうなっているようなチームにしたいと思っています。勝とうが負けようが、終わってすぐにセンターに集まれるような状況ではなく、ピッチに『うわー』って倒れ込む。そんなチームにしたい。10試合後には全員がそうなっているように、1試合目からアプローチしていきたい。試合終了の笛が鳴ったとき、サポーターの人にも、選手たちは力を出し切っていたよねって感じてもらえるような、何かを残したい。そういうチームでありたいと思います」
ユメセンや解説で鍛えられているだけあって、話すトーンには熱があり、口を伝う言葉には魂がこもっている。かつ、話題が豊富で会話は尽きることがない。こちらが気を遣わなければ、いくらでもインタビューは続いていただろう。
最後に若き指揮官は、「チームは愛されてなんぼだと思っている」と語った。だからこそ、選手たちには勝利へこだわり、力を出し切ることを求め、訴える。シーズンは残り10試合——戦っていく過程で、積み重ねていく過程で、選手たちが力を出し切るその姿、その変化を目に焼き付けてほしい。
 J3リーグ第20節を終えて8勝6分6敗の7位と燻っている成績に加え、天皇杯神奈川県予選準決勝で敗退したことにより、8月18日、指揮を執っていた薩川了洋前監督がクラブに辞任を申し出た。
後任として、急遽SC相模原の指揮を託されたのは安永聡太郎だった。監督経験はなく、指揮官としての手腕は未知数である。ただ、その胸にはスペインで学んだ確固たる哲学と、解説者として活動する間もぶれることのなかった揺るぎない信念がある。
今シーズンのJ3リーグも残り10試合——安永新監督はいかなるチームを築こうとしているのか。そのコンセプトを聞く前に、まずは突然の監督就任を引き受けた決意と背景に耳を傾ける。
監督就任はほぼ即答で引き受けた
——SC相模原の監督就任が決まったのが8月20日。シーズン途中での監督就任ですが、自身にとって初の監督業でもあります。率直にどのような思いで引き受けたのでしょうか。
「ずっと監督としてチームを率いてみたいとは思っていたんですよね。一度、指導者の勉強を兼ねてスペインに行き、セグンダB(3部)のCDギフェロというクラブでコーチ契約をしてもらえたんです。ただ、クラブの財政が苦しく、無報酬ならば、という条件でした。ルベン・デ・ラ・バレーラという素晴らしい監督にも出会え、そこで指導者としての一歩を踏み出したいなと思っていたのですが、やっぱり、家族のことを考えると、さすがに無茶はできなかった。それで、しぶしぶ日本に帰ってきたのですが、帰国当初は凹みましたよね。それまで、自分の中に『これだ』というサッカーへの理論はありましたが、いかんせん、現場で指導してみなければ分からないことも多かった。だからこそ、どうせ指導するならば、自分が感銘を受けているスペインで始めたかった。本当にそう思えるほど、CDギフェロで出会ったルベンという監督とは、戦術的な話がたくさんできる間柄だったんです」
——スペインで指導者としてスタートを切るという夢を断念して帰国してからは、再びサッカー解説者をされていましたよね。
「だから、オレは指導者としても“できる”というところを見せたくて、ついつい解説のときにも、自分の理論を口にしていたんですよね。正直、自分にとって、解説の仕事をしているときは、指導者としてのアピールの場だとも考えていたんです。だから、オレはここまで見ているぞ、ここまで分かっているぞというのをついつい言ってしまう。そのせいで視聴者の中には、言い過ぎだろうとか、上から目線だと感じた人もいたでしょうね」
——確かに解説をしているときの印象は、他とは異なるというか色が濃かったというか、具体的に自分の考えを言葉として表現する人だなというイメージがありました。特に言葉をすごく大切にしているなと。
「自分でも言葉の重要性、伝えるということはかなり意識していますね。というのも、現役を引退してから約10年間、JFAこころのプロジェクト『ユメセン』に携わらせてもらいました。そこでは単純計算しただけでも、3万人近い子どもたち、1500人くらいの担任の先生、そして、300人を越える夢先生と一緒に活動し、触れ合ってきました。その活動を通して学んだことが、それはもう、大きかったんですよね。言葉の伝え方、当たり前だけど、それぞれの考え方の違い、また他競技の選手たちからは、個人種目と団体種目における考え方の違いについても勉強させてもらった。特にサッカー選手とは違って、オリンピック選手は365日×4年分の1(1日)にピークを持っていかなければならない。その難しさたるや……オリンピックに出場する過程での苦悩……葛藤を聞かせてもらった。その上で、みんな、4年後を見るのではなく、1日、1日を見て取り組むことの重要性を語っていました。今の自分に何ができるのかということの積み重ねが、4年後の1日につながると」
——サッカー人、指導者としての安永聡太郎だけでなく、人間・安永聡太郎を形成する上でも、JFAこころのプロジェクトで得たことは大きかったんですね。
「本当にそうですね。他には、学校によっても、担任の先生によっても、子どもたちによってもクラスの雰囲気は違ったので、そのときどきで、伝え方を変えなければならなかった。その都度、その都度、雰囲気を感じ取ってアプローチの方法を変えなければ、こちらのメッセージをきちんと伝えることはできないんです。そこは、まさにサッカーの指導にも通じるところがあると思っています。本当に、JFAこころのプロジェクトに10年間携われたことは、今後の自分の指導に活きてくると、自負しています。あの経験は必ず財産になると」
——他にもCPサッカー(脳性麻痺7人制サッカー)の日本代表監督として指導にも当たっていましたよね。
「あの経験も本当に素晴らしい経験になりました。それまでCPサッカーがどんなものかは知らなかったのですが、選手たちと触れ合う中で、彼らのことを理解していきました。CPサッカーはGKを含めた7人制なのですが、フィールドの6人をどう配置して戦うか。対戦相手もいる中で、絶対にやられてはいけないところを伝え、それを選手たちが実行してくれた。同時に強く言うことで意識させすぎてしまうことの難しさも知った。個人としては勝負の世界に身を置いていることが、たまらなく充実していて、大会が終わったときには少し抜け殻になっていたんですよね。また、指導者としてその機微を味わいたいなと。そう思っていたときに、SC相模原から監督就任の話をもらった。短期間で、いろいろと考えましたけど、やるしかないだろうと思い、ほぼ即答で引き受けました」
J3リーグ第20節を終えて8勝6分6敗の7位と燻っている成績に加え、天皇杯神奈川県予選準決勝で敗退したことにより、8月18日、指揮を執っていた薩川了洋前監督がクラブに辞任を申し出た。
後任として、急遽SC相模原の指揮を託されたのは安永聡太郎だった。監督経験はなく、指揮官としての手腕は未知数である。ただ、その胸にはスペインで学んだ確固たる哲学と、解説者として活動する間もぶれることのなかった揺るぎない信念がある。
今シーズンのJ3リーグも残り10試合——安永新監督はいかなるチームを築こうとしているのか。そのコンセプトを聞く前に、まずは突然の監督就任を引き受けた決意と背景に耳を傾ける。
監督就任はほぼ即答で引き受けた
——SC相模原の監督就任が決まったのが8月20日。シーズン途中での監督就任ですが、自身にとって初の監督業でもあります。率直にどのような思いで引き受けたのでしょうか。
「ずっと監督としてチームを率いてみたいとは思っていたんですよね。一度、指導者の勉強を兼ねてスペインに行き、セグンダB(3部)のCDギフェロというクラブでコーチ契約をしてもらえたんです。ただ、クラブの財政が苦しく、無報酬ならば、という条件でした。ルベン・デ・ラ・バレーラという素晴らしい監督にも出会え、そこで指導者としての一歩を踏み出したいなと思っていたのですが、やっぱり、家族のことを考えると、さすがに無茶はできなかった。それで、しぶしぶ日本に帰ってきたのですが、帰国当初は凹みましたよね。それまで、自分の中に『これだ』というサッカーへの理論はありましたが、いかんせん、現場で指導してみなければ分からないことも多かった。だからこそ、どうせ指導するならば、自分が感銘を受けているスペインで始めたかった。本当にそう思えるほど、CDギフェロで出会ったルベンという監督とは、戦術的な話がたくさんできる間柄だったんです」
——スペインで指導者としてスタートを切るという夢を断念して帰国してからは、再びサッカー解説者をされていましたよね。
「だから、オレは指導者としても“できる”というところを見せたくて、ついつい解説のときにも、自分の理論を口にしていたんですよね。正直、自分にとって、解説の仕事をしているときは、指導者としてのアピールの場だとも考えていたんです。だから、オレはここまで見ているぞ、ここまで分かっているぞというのをついつい言ってしまう。そのせいで視聴者の中には、言い過ぎだろうとか、上から目線だと感じた人もいたでしょうね」
——確かに解説をしているときの印象は、他とは異なるというか色が濃かったというか、具体的に自分の考えを言葉として表現する人だなというイメージがありました。特に言葉をすごく大切にしているなと。
「自分でも言葉の重要性、伝えるということはかなり意識していますね。というのも、現役を引退してから約10年間、JFAこころのプロジェクト『ユメセン』に携わらせてもらいました。そこでは単純計算しただけでも、3万人近い子どもたち、1500人くらいの担任の先生、そして、300人を越える夢先生と一緒に活動し、触れ合ってきました。その活動を通して学んだことが、それはもう、大きかったんですよね。言葉の伝え方、当たり前だけど、それぞれの考え方の違い、また他競技の選手たちからは、個人種目と団体種目における考え方の違いについても勉強させてもらった。特にサッカー選手とは違って、オリンピック選手は365日×4年分の1(1日)にピークを持っていかなければならない。その難しさたるや……オリンピックに出場する過程での苦悩……葛藤を聞かせてもらった。その上で、みんな、4年後を見るのではなく、1日、1日を見て取り組むことの重要性を語っていました。今の自分に何ができるのかということの積み重ねが、4年後の1日につながると」
——サッカー人、指導者としての安永聡太郎だけでなく、人間・安永聡太郎を形成する上でも、JFAこころのプロジェクトで得たことは大きかったんですね。
「本当にそうですね。他には、学校によっても、担任の先生によっても、子どもたちによってもクラスの雰囲気は違ったので、そのときどきで、伝え方を変えなければならなかった。その都度、その都度、雰囲気を感じ取ってアプローチの方法を変えなければ、こちらのメッセージをきちんと伝えることはできないんです。そこは、まさにサッカーの指導にも通じるところがあると思っています。本当に、JFAこころのプロジェクトに10年間携われたことは、今後の自分の指導に活きてくると、自負しています。あの経験は必ず財産になると」
——他にもCPサッカー(脳性麻痺7人制サッカー)の日本代表監督として指導にも当たっていましたよね。
「あの経験も本当に素晴らしい経験になりました。それまでCPサッカーがどんなものかは知らなかったのですが、選手たちと触れ合う中で、彼らのことを理解していきました。CPサッカーはGKを含めた7人制なのですが、フィールドの6人をどう配置して戦うか。対戦相手もいる中で、絶対にやられてはいけないところを伝え、それを選手たちが実行してくれた。同時に強く言うことで意識させすぎてしまうことの難しさも知った。個人としては勝負の世界に身を置いていることが、たまらなく充実していて、大会が終わったときには少し抜け殻になっていたんですよね。また、指導者としてその機微を味わいたいなと。そう思っていたときに、SC相模原から監督就任の話をもらった。短期間で、いろいろと考えましたけど、やるしかないだろうと思い、ほぼ即答で引き受けました」
 戦えない、走れない…攻守の切り替えが遅い。
SC相模原の監督就任を打診され、実際に指導に当たるまでには、わずかな時間しかなかった。限られた時間の中で見たSC相模原の試合で、安永監督が感じた課題とは何だったのか。
自身も「細かくて、しつこい」と笑うように、練習では具体的な指示がいくつも飛んでいる。常に大声を張り上げ、選手たちに訴えかけているため、のど飴が必需品になっているという。分析した課題であり、そのアプローチ方法を知れば、新たなるスタートを切るSC相模原のコンセプトが見えてくる。
——指導前に試合の映像を見たそうですが、そこで感じたチームへの課題とは?
「まず感じたのは、戦えない、走れない……攻守の切り替えが遅いというところでしたね。練習をはじめて、すぐにそれを選手たちにも言いました。走れないのは、純粋に走れないのか、それとも走りたいけど走り方が分からないのか。そこは映像だけでは判断できず、直接、指導する中で確認したいと思っていました」
——実際に練習で指導してみて、どっちだったんですか?
「両方でしたね。実際、単純に走れていないところもありました。一方で、走り方を指示してみても、走ろうとするけど、その走り方が分かっていなかった。例えば、サイドの選手がどこにポジションを取っているのか、ボールを動かしているときに自分は何をしたらいいのかが分かっていなかった。特に顕著だったのは、ボールを動かすことにこだわるがゆえに、みんながボールを受けに戻ってくるため、すべてのプレーが後ろ向きになっていたんですよね。後ろ向きにプレーするから、相手は前向きにプレッシャーを掛けられる。そこで自分たちは苦しくなるから、前に蹴りますよね。でも、そこでも後ろ向きに戻ってきているからセカンドボールを拾われてしまう。その繰り返しだったんです。だから、選手たちには、基本的に後ろ向きでボールを受けるなということを言いました。前、もしくは横を向いた状態でボールを受けられるようにしようと。ポゼッションするけれども、まずはポジションプレーなんですよね。正確なポジションを各々が取ることで、ポゼッションしているところでは、相手に圧を掛けさせないようにできる」
——サッカーはゴールを奪うスポーツです。そのためにも、前向きでプレーする意識は重要かもしれませんね。
「正確なポジションを取っていても、相手が無理にプレスを掛けてきたのであれば、オレはそのボールを蹴ってもいいと思っています。そのときはどこかで必ず数的優位か数的同数の状況が作れているはずだから。そこで相手とのボールの奪い合いが起こったとしても、周りや相手には偶然に見えるかもしれないけど、オレの考え方としては、それは必然になる。チームのコンセプトとしては、偶然を必然に変える作業をどれだけできるか。うちのチームにおいて、『ラッキーだったね』というプレーはないようにしたい。プレーのひとつひとつが起こるべくして起きたプレーになる。そして、そのためにチームとしての共通認識というものが重要になってくる」
戦えない、走れない…攻守の切り替えが遅い。
SC相模原の監督就任を打診され、実際に指導に当たるまでには、わずかな時間しかなかった。限られた時間の中で見たSC相模原の試合で、安永監督が感じた課題とは何だったのか。
自身も「細かくて、しつこい」と笑うように、練習では具体的な指示がいくつも飛んでいる。常に大声を張り上げ、選手たちに訴えかけているため、のど飴が必需品になっているという。分析した課題であり、そのアプローチ方法を知れば、新たなるスタートを切るSC相模原のコンセプトが見えてくる。
——指導前に試合の映像を見たそうですが、そこで感じたチームへの課題とは?
「まず感じたのは、戦えない、走れない……攻守の切り替えが遅いというところでしたね。練習をはじめて、すぐにそれを選手たちにも言いました。走れないのは、純粋に走れないのか、それとも走りたいけど走り方が分からないのか。そこは映像だけでは判断できず、直接、指導する中で確認したいと思っていました」
——実際に練習で指導してみて、どっちだったんですか?
「両方でしたね。実際、単純に走れていないところもありました。一方で、走り方を指示してみても、走ろうとするけど、その走り方が分かっていなかった。例えば、サイドの選手がどこにポジションを取っているのか、ボールを動かしているときに自分は何をしたらいいのかが分かっていなかった。特に顕著だったのは、ボールを動かすことにこだわるがゆえに、みんながボールを受けに戻ってくるため、すべてのプレーが後ろ向きになっていたんですよね。後ろ向きにプレーするから、相手は前向きにプレッシャーを掛けられる。そこで自分たちは苦しくなるから、前に蹴りますよね。でも、そこでも後ろ向きに戻ってきているからセカンドボールを拾われてしまう。その繰り返しだったんです。だから、選手たちには、基本的に後ろ向きでボールを受けるなということを言いました。前、もしくは横を向いた状態でボールを受けられるようにしようと。ポゼッションするけれども、まずはポジションプレーなんですよね。正確なポジションを各々が取ることで、ポゼッションしているところでは、相手に圧を掛けさせないようにできる」
——サッカーはゴールを奪うスポーツです。そのためにも、前向きでプレーする意識は重要かもしれませんね。
「正確なポジションを取っていても、相手が無理にプレスを掛けてきたのであれば、オレはそのボールを蹴ってもいいと思っています。そのときはどこかで必ず数的優位か数的同数の状況が作れているはずだから。そこで相手とのボールの奪い合いが起こったとしても、周りや相手には偶然に見えるかもしれないけど、オレの考え方としては、それは必然になる。チームのコンセプトとしては、偶然を必然に変える作業をどれだけできるか。うちのチームにおいて、『ラッキーだったね』というプレーはないようにしたい。プレーのひとつひとつが起こるべくして起きたプレーになる。そして、そのためにチームとしての共通認識というものが重要になってくる」
 ——偶然を必然に変える。それを具現化するために目指すサッカーとは?
「我々はプロだから、まず試合に勝たなければならないですよね。大前提として、勝つために何ができるかというのがある。だから、対戦する時点での自分たちと、相手との力量によっても戦い方は変わってくると思っています。相手のほうが強く、前からプレッシャーを掛けてくるチームに対して、今のチームの現状で後ろからつなげば、相手の守備にハメられてしまう確率は高い。それならば、極端な話、オレは蹴るサッカーを選択する。だから、どういうサッカーを目指しますかと聞かれると、答えられないかもしれない(笑)」
——こちらから聞いておいて、あれですが、ちょっと分かる気がします。日本は多くのチームが自分たちのサッカー、自分たちのサッカーと提唱しすぎる傾向がありますよね。
「ですよね? よくバルセロナみたいなサッカーを目指すと言う話を聞きますけど、純粋にすごいなと思ってしまうところがあります。バルセロナはバルセロナだから、あの戦い方を貫ける。そこには(リオネル・)メッシがいて、何十億円もの資金を投じて、より目指すサッカーを強固にして、具体化できる。世界を見ても、それを貫けているのはバルセロナくらい。でも、オレはどの試合も勝ちたいから、まずは相手を分析して、この相手には何をすれば一番、勝率が上がるかを考える。どうすれば効果的なのかを考えた上でメンバーも選び、変えていくつもりです。ただし、チームとして統一感のない試合をするつもりはありません。ピッチに立った選手がそれぞれ11km近くをバラバラに走るのではなく、直線(前向き)に走ることで、総合的に120kmにしたい。もちろん、試合中にそのすべての状況を作るのが難しいことは分かっています。でも、ぶれずにやっていきたいなと」
——結果を求めるために、相手によって戦い方を変えていくということですよね?
「そうですね。育成年代であれば別ですが、プロである以上、結果を追い求めていきたい。SC相模原でも、ボールをつなぐようなサッカーをしたいですが、先ほども言ったように、苦しければ蹴ってもいい。ただし! それには必ず、人が降りてくるようにしたい。蹴りっぱなしにならないこと。蹴ったらラインを上げて、セカンドボールを拾う準備をする。攻められている同サイドに必ずFWが降りてくる。それによって同サイドにクリアした場合は、ボールを拾える可能性がゼロではなくなっているわけですからね。相手よりも実力があると判断すればつなぎます。そのときは、1週間、ボールをつないで相手を外す、崩す練習を取り入れていく。前線には狭いエリアでつなげる選手を配置しなければならないから、当然、そのときはメンバーも変わってきますよね。要するに、相手の長所と短所をしっかりと見極めて、戦っていきたい。そのためにみっちり練習して、選手たちには必死についてきてもらう代わりに、試合で起こったことの責任はすべてオレにあると思っています。選手たちには、その上で、個々に責任と自由があって、チームプレーにおいての責任は与えます。ただ、それを判断するのも選手たち自身。チームとしてやろうとしていることと違う選択をして失敗したときには、その代わり責任は取ってもらうよと。それはメンバーを変えることかもしれないし、途中交代という形になるかもしれないですけどね。ただ、監督が言うことだけをやっているだけでは、サッカーは面白くないですよね。だから、すべてにおいて状況判断が大事なんです。ピッチ全体を3つのエリア(ディフェンディングサード、ミドルサード、アタッキングサード)に分けた場合、ここ(ミドルサード)まではチームとしての約束ごとがある。でも、ここ(アタッキングサード)まで来たら、選手たちの自由だよと思っている。そこに到達したときには、それまで制限されていたわけだから、自分の個性を思いっ切り解放してほしいなと思っています」
——自分自身でも試行錯誤しながらの日々だとは思いますが、練習を見ていても充実していることは感じます。
「この方向性が良いのか悪いのかも含めて、正直、経験がないので判断はできません(笑)。でも、誰もが、そうであるように経験はやらなければ積むことはできない。本当に日々、良い勉強をさせてもらっていると思っていますし、クラブには感謝しています。選手には迷惑を掛けているかもしれないですが、そこはお互いにリスペクトしてやっていければと思っています。毎試合、勝利のため、勝つということにこだわってやっていきたい。それで90分が終わったときに、ピッチに倒れ込む選手がどれだけいるか。10試合終わったときには、ピッチにいる全員がそうなっているようなチームにしたいと思っています。勝とうが負けようが、終わってすぐにセンターに集まれるような状況ではなく、ピッチに『うわー』って倒れ込む。そんなチームにしたい。10試合後には全員がそうなっているように、1試合目からアプローチしていきたい。試合終了の笛が鳴ったとき、サポーターの人にも、選手たちは力を出し切っていたよねって感じてもらえるような、何かを残したい。そういうチームでありたいと思います」
ユメセンや解説で鍛えられているだけあって、話すトーンには熱があり、口を伝う言葉には魂がこもっている。かつ、話題が豊富で会話は尽きることがない。こちらが気を遣わなければ、いくらでもインタビューは続いていただろう。
最後に若き指揮官は、「チームは愛されてなんぼだと思っている」と語った。だからこそ、選手たちには勝利へこだわり、力を出し切ることを求め、訴える。シーズンは残り10試合——戦っていく過程で、積み重ねていく過程で、選手たちが力を出し切るその姿、その変化を目に焼き付けてほしい。
——偶然を必然に変える。それを具現化するために目指すサッカーとは?
「我々はプロだから、まず試合に勝たなければならないですよね。大前提として、勝つために何ができるかというのがある。だから、対戦する時点での自分たちと、相手との力量によっても戦い方は変わってくると思っています。相手のほうが強く、前からプレッシャーを掛けてくるチームに対して、今のチームの現状で後ろからつなげば、相手の守備にハメられてしまう確率は高い。それならば、極端な話、オレは蹴るサッカーを選択する。だから、どういうサッカーを目指しますかと聞かれると、答えられないかもしれない(笑)」
——こちらから聞いておいて、あれですが、ちょっと分かる気がします。日本は多くのチームが自分たちのサッカー、自分たちのサッカーと提唱しすぎる傾向がありますよね。
「ですよね? よくバルセロナみたいなサッカーを目指すと言う話を聞きますけど、純粋にすごいなと思ってしまうところがあります。バルセロナはバルセロナだから、あの戦い方を貫ける。そこには(リオネル・)メッシがいて、何十億円もの資金を投じて、より目指すサッカーを強固にして、具体化できる。世界を見ても、それを貫けているのはバルセロナくらい。でも、オレはどの試合も勝ちたいから、まずは相手を分析して、この相手には何をすれば一番、勝率が上がるかを考える。どうすれば効果的なのかを考えた上でメンバーも選び、変えていくつもりです。ただし、チームとして統一感のない試合をするつもりはありません。ピッチに立った選手がそれぞれ11km近くをバラバラに走るのではなく、直線(前向き)に走ることで、総合的に120kmにしたい。もちろん、試合中にそのすべての状況を作るのが難しいことは分かっています。でも、ぶれずにやっていきたいなと」
——結果を求めるために、相手によって戦い方を変えていくということですよね?
「そうですね。育成年代であれば別ですが、プロである以上、結果を追い求めていきたい。SC相模原でも、ボールをつなぐようなサッカーをしたいですが、先ほども言ったように、苦しければ蹴ってもいい。ただし! それには必ず、人が降りてくるようにしたい。蹴りっぱなしにならないこと。蹴ったらラインを上げて、セカンドボールを拾う準備をする。攻められている同サイドに必ずFWが降りてくる。それによって同サイドにクリアした場合は、ボールを拾える可能性がゼロではなくなっているわけですからね。相手よりも実力があると判断すればつなぎます。そのときは、1週間、ボールをつないで相手を外す、崩す練習を取り入れていく。前線には狭いエリアでつなげる選手を配置しなければならないから、当然、そのときはメンバーも変わってきますよね。要するに、相手の長所と短所をしっかりと見極めて、戦っていきたい。そのためにみっちり練習して、選手たちには必死についてきてもらう代わりに、試合で起こったことの責任はすべてオレにあると思っています。選手たちには、その上で、個々に責任と自由があって、チームプレーにおいての責任は与えます。ただ、それを判断するのも選手たち自身。チームとしてやろうとしていることと違う選択をして失敗したときには、その代わり責任は取ってもらうよと。それはメンバーを変えることかもしれないし、途中交代という形になるかもしれないですけどね。ただ、監督が言うことだけをやっているだけでは、サッカーは面白くないですよね。だから、すべてにおいて状況判断が大事なんです。ピッチ全体を3つのエリア(ディフェンディングサード、ミドルサード、アタッキングサード)に分けた場合、ここ(ミドルサード)まではチームとしての約束ごとがある。でも、ここ(アタッキングサード)まで来たら、選手たちの自由だよと思っている。そこに到達したときには、それまで制限されていたわけだから、自分の個性を思いっ切り解放してほしいなと思っています」
——自分自身でも試行錯誤しながらの日々だとは思いますが、練習を見ていても充実していることは感じます。
「この方向性が良いのか悪いのかも含めて、正直、経験がないので判断はできません(笑)。でも、誰もが、そうであるように経験はやらなければ積むことはできない。本当に日々、良い勉強をさせてもらっていると思っていますし、クラブには感謝しています。選手には迷惑を掛けているかもしれないですが、そこはお互いにリスペクトしてやっていければと思っています。毎試合、勝利のため、勝つということにこだわってやっていきたい。それで90分が終わったときに、ピッチに倒れ込む選手がどれだけいるか。10試合終わったときには、ピッチにいる全員がそうなっているようなチームにしたいと思っています。勝とうが負けようが、終わってすぐにセンターに集まれるような状況ではなく、ピッチに『うわー』って倒れ込む。そんなチームにしたい。10試合後には全員がそうなっているように、1試合目からアプローチしていきたい。試合終了の笛が鳴ったとき、サポーターの人にも、選手たちは力を出し切っていたよねって感じてもらえるような、何かを残したい。そういうチームでありたいと思います」
ユメセンや解説で鍛えられているだけあって、話すトーンには熱があり、口を伝う言葉には魂がこもっている。かつ、話題が豊富で会話は尽きることがない。こちらが気を遣わなければ、いくらでもインタビューは続いていただろう。
最後に若き指揮官は、「チームは愛されてなんぼだと思っている」と語った。だからこそ、選手たちには勝利へこだわり、力を出し切ることを求め、訴える。シーズンは残り10試合——戦っていく過程で、積み重ねていく過程で、選手たちが力を出し切るその姿、その変化を目に焼き付けてほしい。